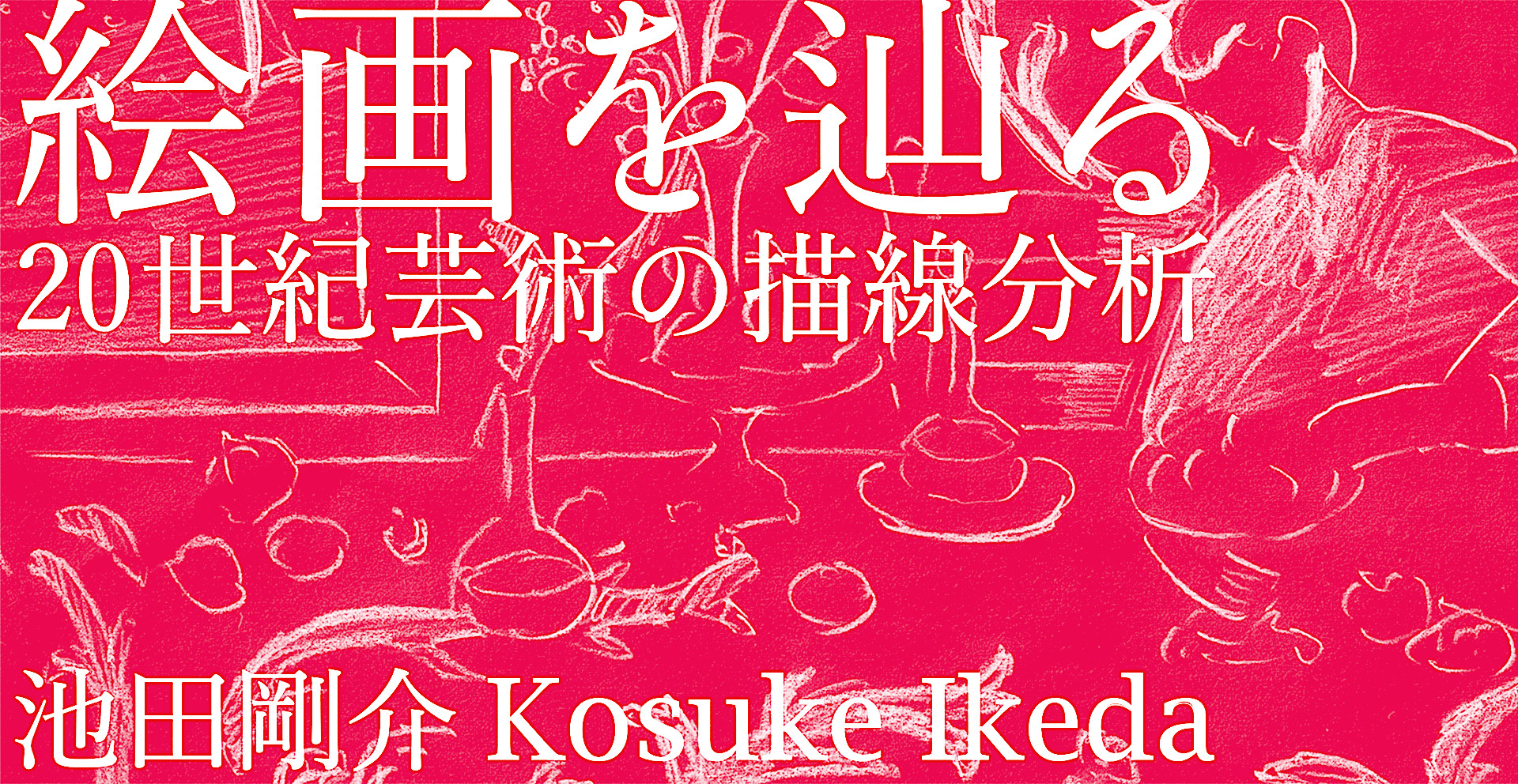京都を拠点に活動する美術作家・批評家の池田剛介さんによる、20世紀の絵画の「描線(ドローイング)」をテーマにした連載です。作品に描かれた「動き」や「身振り」としての線に注目することで、「これまで見えていなかった作品の姿」を明らかにします。第十二回は、東京国立近代美術館のコレクション展で展示されている桂ゆきについてです。ぜひ展示とあわせてお楽しみ下さい。
ギリシア人は単純な調和を愛したから、円をうつくしいと感じたでもあろうが、矛盾しているにも拘らず調和している、楕円の複雑な調和のほうが、我々にとっては、いっそう、うつくしい筈ではなかろうか。[1]
グチャグチャとした紙くずに枯れ草や押花——絵画の中央には生活のなかの様々な物体の断片が、乱雑にちらばるかのようである。このゴミの散乱した家のような印象とは裏腹に、作品の原題は《賀象》という。聞きなれない言葉だが、「賀=寿ぐ」「象=イメージ」ということだろう。はたしてこの絵画は何を寿いでいるというのだろうか(図1)。

図1 桂ゆき《作品》(原題:《賀象》)1940年
2025年の夏、東京国立近代美術館のコレクション展の会場に、1940年に制作された作品を集めた一角があった。桂ゆきによる本作は、そのなかの一点である。
日中戦争の開戦から三年、翌年の太平洋戦争の開戦を目前にした1940年は、神武天皇が即位して2600年目にあたることから紀元(皇紀)2600年と呼ばれ、内向きには国家主義的な空気を醸成し、対外的には国力を誇示すべく、さまざまな行事が計画された。
この年、東京ではオリンピックと万博が同時期に開催される予定となっていたが、日中戦争の長期化や国際連盟からの脱退による国際的な孤立といった状況で実現できるはずもなく、どちらも幻と消えている。万博やオリンピックといった国家的な事業が頓挫するなか、「紀元二千六百年 奉祝美術展覧会」と題された美術展が上野の東京府美術館(現・東京都美術館)で開催された。作品はこの展覧会に出品されたものである。
《賀象》という原題は、この紀元2600年の奉祝という展覧会の文脈に関連してもいるだろう。改めて作品を見てみると、画面の右上部に赤い色のエリアが現れてくる(図2)。一方は大きく羽を広げ、もう一方はその力を受け止めるかのような一対の鳥は、古くから祝いのモチーフとして用いられる鴛鴦だろう。細かく縦方向に刻まれた筆致は、それが刺繍のような印象も与え、いずれにせよ周囲の紙くずとは微妙に異なる質感が与えられている。とはいえ、その菱形は半ば周囲のゴミに埋もれかけてもいる。

図2 《作品》部分、撮影筆者
先に思わず「ゴミの散乱した家」と記したが、本作は背景に立ち上がるスクリーン状の白によって閉じられた室内のような印象を与える。と同時に、その両端から覗く空間は屋外のようでもある。屋外に開かれた舞台状の床に立ち上がる、部分的に閉じた空間とでも言うべきだろうか。いずれにせよ屋外とも屋内ともつかない、あるいはその両者が相互浸透するかのような奇妙な空間において、雑多な断片たちが圧縮されるように犇めきあっている。
「ぜいたくは敵だ」というスローガンが広がったこの1940年、紙くずや布切れによって表される「貧しさ」を受け入れることによって国家的なものを支えているように受け取ることができなくもない。だが作品は、右上に掲げられた祝いのモチーフと同等か、あるいはそれ以上に、それをかろうじて支える断片にこそ関心を寄せているようにも感じられる。この祝いと猥雑さ、聖的なものと俗的なものとが混在するかのような謎めいたイメージは、いかに生み出されたのだろうか。
コラージュから始まる
東京帝国大学(現・東京大学)で非鉄金属を専門とする教授の娘として1913年に生まれた桂ゆきは、「親子はおろか兄弟姉妹の間ですら他人行儀の言葉を使うようなとりすました家庭環境」[2]、つまりはゴミの散乱した猥雑さとは真逆の環境で育てられたという。油絵を学ぶことを希望していたものの、「裸を描いたり油絵具だらけになったり、それは男子のすることで嫁入り前の娘の“たしなみ”としては適当でない」[3]ということではねのけられ、日本画家のもとに通っている。
日本画の手習いを通じて、花や鳥など日本画ではお馴染みのモチーフの写生や模写を行う一方で、周囲から求められる行儀の良さから密かに逸脱するような手つきの感じられる17歳の女学校時代の作品が残されている。
海に浮かぶ島が映された風景写真を小さく手でちぎりながら再構成した、ハガキよりもひとまわり小さな作品である(図3)。写真は海や岩といったイメージを映し出す一方で、そのちぎられた周辺では、写真のイメージによって隠れていた白の紙の質感があらわになる。破れた紙の質感は、先に見た紙くずによる作品を予告するかのようだ。

図3 桂ゆき 作品名不詳 1930年
そこから数年が経ち、当時の女性作家としては稀なことだが、前衛的な作風を探求するアヴァンガルド洋画研究所に通い始めている。ここで布やレース、植物などを画面に直接貼りつけていく制作を模索し、1935年にはこれらのコラージュ作品による初個展を行なった。この時期、桂は二階から周囲の屋根瓦を見下ろしながら、同一物が無限に反復していく光景に啓示のようなものを受け、近所の工場で廃材として捨てられていたコルクを用いた制作に取り組んでいる(図4)。

図4 桂ゆき《作品(コルク)》1935年
瓦の凹凸の反転したような窪んだカーブをもつコルクを敷きつめた作品には、伝統的な遠近法に基づくことのない画面が現れている。小さな矩形がタイル状に敷き詰められた画面は、写真をちぎりながら貼り込んでいく作品とも連続した関心を感じさせる。
こうして平面的な物質を画面に貼りつけていくコラージュに取り組む一方で、このコルクによるコラージュを元に絵画を描くという、入り組んだプロセスをもつ作品にも取り組んでいる(図5)(第六回でも紹介したように、コラージュに先駆的に取り組んだブラックやピカソも、自ら制作したコラージュに基づく絵画を描いている)。

図5 桂ゆき《ひなた》1935年
中央左手の大きなコルクの形状や質感など、先のコラージュを克明に再現する部分をもちながら、画面全域を覆う比較的均質だったコルクの大きさには変化が与えられ、ある部分ではロール状に大きく捲れ上がりながら、その凹凸が誇張されている。こうした観る者の方に迫り出すかのような要素、また褐色の断片のなかに赤みを帯びた花が埋もれていくような様は、後の《賀象》を思わせるものでもある。
積み上げと貼り付け
コラージュへの傾注とも関連して、桂にとって重要な問題は、当時の前衛的動向として紹介されたばかりのシュルレアリスムだろう。桂が通い始めたアヴァンガルド洋画研究所は、クレーから大きな影響を受けたのちに独自のシュルレアリスムを展開した古賀春江の尽力によって創設され、開設から間もなくして古賀は病で亡くなるものの、東郷青児や藤田嗣治といった前衛画家らが講師として参加していた。
こうした前衛、とりわけシュルレアリスムの傾向の色濃い環境で作品を展開していく一方で、当時のダリの流行を通じて、30年代後半から日本の前衛に頻繁に見られるようになった「地平線のある絵」に対しては批判的な視点をもっていたことが知られている[4]。「当時はフランスからのシュルレアリスムが新しいものでした。私はそれを鵜呑みにしたような絵は絶対に描きたくないと思ってました」[5]。
冒頭で見た《賀象》は、シュルレアリスムに大きな影響を与えた画家、ジョルジョ・デ・キリコの作品を一つの参照元にしている可能性が指摘されている[6]。1932年に東京府美術館で開催された巴里新興美術展覧会に、このデ・キリコの作品は出品された(図6)。翌年にはアヴァンガルド洋画研究所に通い始めることになる桂が、シュルレアリスムをはじめとして多くの前衛的な作品が集められた、本郷の自宅からほど近い上野での展覧会を見ていたとしても全く不思議ではないだろう。

図6 ジョルジョ・デ・キリコ《戦勝標》1926年
雑多な物体が台形の白地を背景に立ち上がる独特の構成において《賀象》はデ・キリコ作品とたしかに通じている。だが一方で、桂の作品にはそれを鵜呑みにするのではない重要な改変が加えられてもいる。デ・キリコの作品には、積み上がった物体にせよ、背景の白い面にせよ、そこに立体感を表す陰影がはっきりと施されており、三次元的な空間のなかでの雑多な立体物の「積み上げ」の構造が、作品の核となっている。これに対して桂のそれには、中央に密集した物体や背景の白には陰影の表現がほとんどなされておらず、先のコラージュにも通じる平面的な印象を与えるだろう。
もう一つの重要な改変は、デ・キリコ作品の白い背景の上部に見られる、奥行きの空間性を示す雲が消されている点である。桂の作品において立ち上がる白い背景はシュルレアリスム的な空想の産物というよりも、より即物的な平面として扱われている。また《賀象》において描かれている鴛鴦や茶碗、押花は、デ・キリコの作品とは異なり、それぞれにカード状の小さな平面に定着されており[7]、何らかのイメージの表れた平面を再平面(絵画)化するという入れ子状の構造をもつ(図7)。

図7 《作品》部分、撮影筆者
コラージュ的な「貼り付け」を示唆する上での、さらなる重要な要素が、画面のそこここに現れる「染み」のような不定形の形象である(図8)。不定形な染みには、その輪郭を辿る線が付されており、決して偶然的に現れたものではないことが分かるだろう。これらは中央に描かれた断片の上のみならず、背景の白い紙の上部にも複数現れながら、平面的な構造のいくつかの階層を跨いで現れている。

図8 左:《作品》部分、撮影筆者 右:筆者作成
描かれた「染み」について桂は次のように語っている。「手当たりしだい、ボロとか新聞紙とか、レースを使って作ったんです。染みなんかを使ったのもその頃です。雨が漏ってできるような。(…)それは染みそのものであって、しかも染みじゃないということに気を使っています」。
「染みそのものであって、しかも染みじゃない」とはどういうことか。それが通常の染みのように偶然的に現れたそれではなく(つづめて言えば、この偶然性が「染み」と「染め」の違いである)、あくまでも克明に辿られた形であるということだろう。つまり偶然的な染みのようであると同時に、染みとして認識される形象でもあるということだ[8]。「染み」は形象化されることで、あたかもシールのように輪郭を切り抜くことのできるイメージとなり、先に見たように、中央の紙くずや背景の白といった、作品内の複数の異なる平面上を横断することが可能になる[9]。
こうして描かれたイメージの断片は、デ・キリコの作品を基礎構造とすることで、その半面では「積み上げ」という三次元的な構造を踏襲しながら、しかし同時に、白の背景と並行に走る貼り付けられた平面としてのコラージュ的な側面を強調しもする。「積み上げ」と「貼り付け」という相矛盾する表現が、雑多な事物の犇めき合いのなかで圧縮されているのである。
敬虔と猥雑
このデ・キリコの作品がタイトルの通り「戦勝標」をテーマにしていた点もまた示唆的である。この主題は1920年代にデ・キリコが度々描いていたものの一つであり、勝利者側が戦地より持ち帰った武器や略奪品といった品々を並べた、戦勝を記念するトロフィーがモチーフとなっている。
どの程度まで桂がこの作品の戦勝標という主題を意識していたのかは定かではないものの、奉祝を掲げた展覧会への作品において、このテーマが全く念頭になかったとすれば不自然だろう[10]。しかし、この祝いを表す鴛鴦のイメージが紙くずのなかに埋もれていく絵画において、そこに込められた意味合いは、丹念に描き込まれた「染み」がそうであるように、どこまでも不定形=不確定なものである。
「敬虔と猥雑とが、――この最も結びつきがたい二つのものが、同等の権利をもち、同時存在の状態において、一つの額縁のなかに収められ、うつくしい効果を出し得ようなどとは、いまだかつて何人も、想像だにしたことがなかったのだ」[11]。戦時下の43年に花田清輝が詩人のフランソワ・ヴィヨンについて論じた「楕円幻想」の一節である。
鴛鴦のイメージが紙くずや染みと同居する、その「敬虔と猥雑とが」「一つの額縁のなかに収められ」た桂の絵画を見るとき、この批評家の言葉は示唆的であるように思われないだろうか。桂と花田は戦後すぐに交流を始めることになるが、その出会いに先んじた共鳴が、ここにはある。花田は焦点がただ一つに定まった「正円」に対して、二つの焦点をもつ「楕円」の形象に終生こだわり続けた。
楕円は、焦点の位置次第で、無限に円に近づくこともできれば、直線に近づくこともできようが、その形がいかに変化しようとも、依然として、楕円が楕円である限り、それは、醒めながら眠り、眠りながら醒め、泣きながら笑い、笑いながら泣き、信じながら疑い、疑いながら信ずることを意味する。これが曖昧であり、なにか有り得べからざるもののように思われ、しかもみにくい印象を君にあたえるとすれば、それは君が、いまもなお、円の亡霊に憑かれているためであろう。[12]
楕円は二つの焦点をもち、その周辺を軌道とする線である。焦点=軸がけっしてブレることのない正円とは異なり、複数の焦点の位置次第で、その形を柔軟に変化させることができる。「醒めながら眠り、眠りながら醒め、泣きながら笑い、笑いながら泣き、信じながら疑い、疑いながら信ずること」、こうした花田の主張について沼野充義は「右翼であれ、左翼であれ、円の正しさだけを信奉する人々の無理解の中で、自分なりに楕円の論理の筋を通して生きてきた思想家」[13]のスタンスを見出している。
この二つの焦点をもつ楕円のありようは、《賀象》にも通じるものだろう。室内と屋外、積み上げと貼り付けという、相反する空間性の混在とともに、鮮やかな色合いで描かれる祝いのイメージと褐色による不穏さを併せもち、敬虔と猥雑が同居しながら確定的な意味を宙吊りにする。個別の要素は明確に辿ることができるにもかかわらず、複雑に入り組みながら決して出口に辿り着くことのない終わりなき迷宮となるのである。
戦後間もなく桂は、岡本太郎の誘いで前衛芸術の研究グループ「夜の会」に参加し、ここから花田との交流が生まれることとなる。この時期から桂は、日本の土着的なものを取り入れた絵画の制作に取り組み、挿画や絵本や執筆にも活動を広げていく。その複数の焦点をもった制作の軌道を、さらに大きく展開させていくことになるのである。
【注】
[1] 花田清輝「楕円幻想——ヴィヨン——」『花田清輝著作集〈第1巻〉』未来社、1964年、172頁。
[2] 桂ゆき「女ひとり、コラージュ人生 桂ゆき自伝」『女性芸術家の人生② 丑年篇』集英社、1980年、82頁。
[3] 同上、87頁。
[4] 針生一郎「桂ゆき 日常性を変形するユーモア」『わが愛憎の画家たち』平凡社、1983年、207頁。また30年代の日本でのダリの流行に関しては次を参照。速水豊、弘中智子、清水智世編著『シュルレアリスムと日本』青幻舎、2024年、148頁。
[5] インタビュー「桂ゆきの40年——コラージュと諷刺的表現の間で」『みづゑ』893号、1979年、45頁。
[6] 濱本聰「桂ゆき試論——伝統のパロディ、もしくはアイロニーとしての視線」『下関市立美術館紀要』1993年、4頁。
[7] 押し花をはじめとして平面化されたものへの桂の関心については次を参照。関直子「桂ゆきのエニグマ」『平成26年度 東京都現代美術館年報 研究紀要 第17号』2015年、85-91頁。
[8] 桂の「染み」へのこだわりは、例えばマックス・エルンストが《主の寝室》で用いた学校教材用の図像集や、マグリットが好んだ科学雑誌のイラストレーションから借用したイメージを思わせるものだ。鈴木雅雄はシュルレアリストが好んだこうしたイメージのありようを、「眼前に実在する世界であるかのように立ち現れる古典的な絵画と、無限に反復可能な記号的イメージとの中間にある」ものとして「図」として位置づけ、この図の力が複数の作品やメディアを横断するシュルレアリスムに独特の作用をもつことを指摘している。次を参照。鈴木雅雄「「絵」と「記号」のあいだ」、鈴木雅雄、林道郎『シュルレアリスム美術を語るために』水声社、2011年、81–99頁。またシュルレアリストが好んで採用した遠近法については同書の次の議論を参照。林道郎「遠近法―的―空間について」100–127頁。
[10] 出品作を抜粋して掲載した二冊組の記録集『紀元二千六百年 奉祝美術展集』(朝日新聞社、1940年)で確認する限り、時局と関連した画題の選択も多少見られるものの、大部分の作品は個別の制作の延長上にあり、出品にあたって必ずしも奉祝というテーマが強く求められたものではないようである。画題などの選択は、ほぼ出品者に委ねられたと見るべきだろう。
[11] 花田清輝前掲書、173–174頁、強調は引用者。
[12] 同上、172頁、強調は引用者。
[13] 沼田充義「解説」花田清輝『アヴァンギャルド芸術』講談社文芸文庫、1994年、326頁。
【図版出典】
01, 03, 04, 05:『桂ゆき——ある寓話』図録、東京都現代美術館他、2013年
06 :速水豊、弘中智子、清水智世編著『シュルレアリスムと日本』青幻舎、2024年