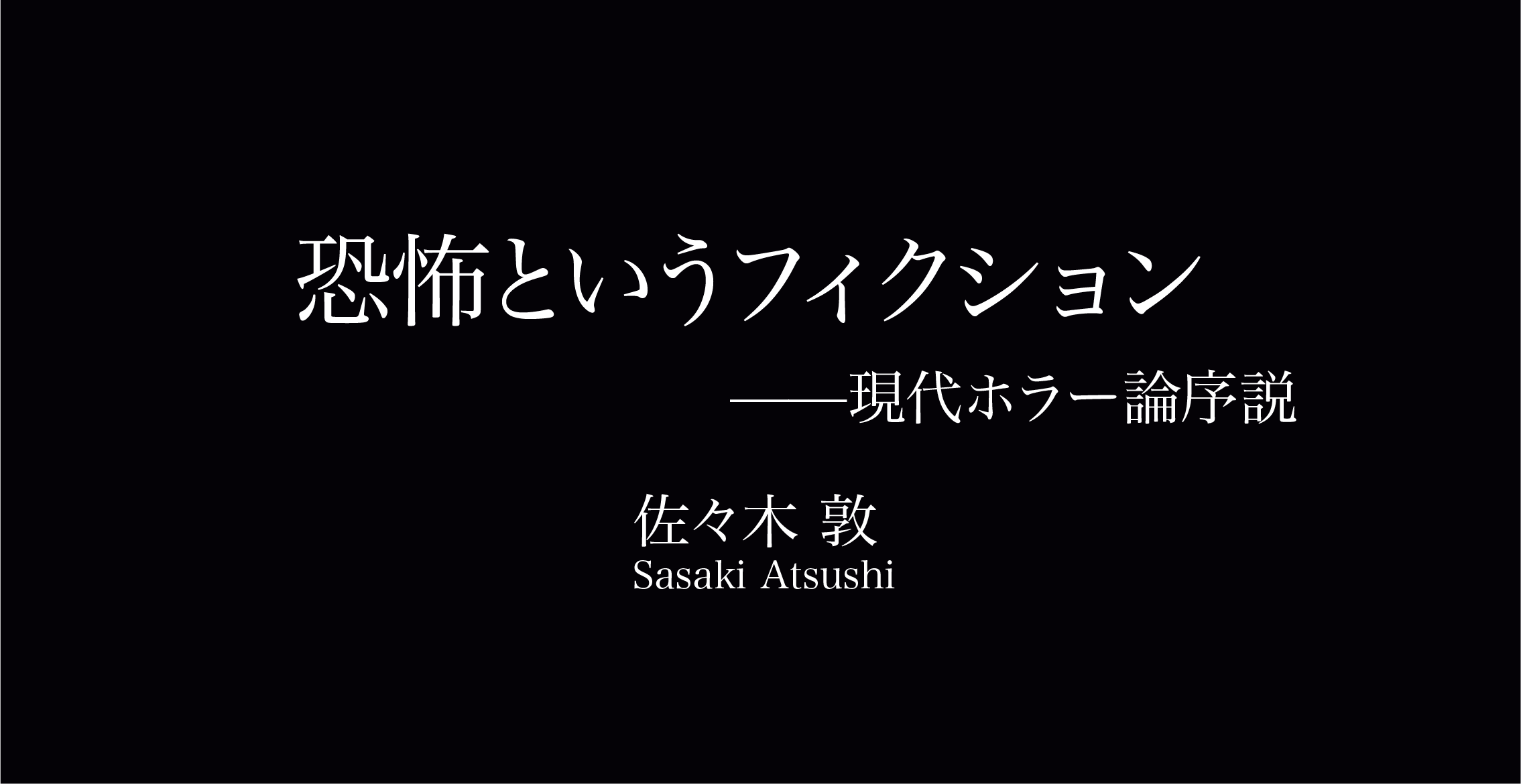佐々木敦さんによる「ホラー」をめぐる新連載が始まります。ひとはなぜ恐怖するのか、ひとはなぜ恐怖を必要とするのか、そもそも恐怖とは何か。わたしたちの普遍的な、しかしあまりにも個別的な情動を通じての、現代のフィクションをめぐる思索の旅をぜひお楽しみください。
前口上
ホラーと呼ばれるジャンルについて考えてみたい。
とはいうものの、私は特に「こわいもの好き」というわけではない。かといって苦手でもない。「こわいもの」は、得意でも不得意でもない。いわゆるホラーファン/マニアとも、私の関心のあり方は多くの点でおそらくかなり違っている。
いや、実を言えば、なぜ自分が「恐怖表現=ホラー」のことを考えてみたいと思っているのか、今も私はよくわかっていないのだ。むしろそれを明らかにすることこそが本連載の目標ということになるのかもしれない。そしてそれは同時に「ひとはなぜホラーに惹かれるのか?」「ひとはなぜホラーを求めるのか?」などといった問いに自分なりの答えを見つけようとする試みにもなることだろう。
そう、私は不思議なのだ。ひとがなぜ「恐怖」を必要とするのか。あるいはそれ以前に、そもそも「人間」にとって「恐怖」とは何なのか?
むろん、こうして論を開始するからには、私にも多少の考えはある。まずはプロローグ代わりに二つの話をしておきたい。体験談とやや理屈めいた話で、二つは繋がっている。それらはこの「現代ホラー論序説」の序であり、全編を貫く力線となる。そしてまた、なぜこの連載が『恐怖というフィクション』と題されているのかを、あらかじめ示唆することにもなるだろう。
では、始めよう。
肝試しとお化け屋敷
私は肝試しに強い。父親の生家は岐阜県の山奥にあり、見渡す限り田畑と森林ばかりで、周囲に他の住居は見当たらず、坂の上に古い墓地があった。子供の頃、親戚の子たちと肝試しをしたり、そのつもりがなくても外で遊んでいるだけで日が暮れると肝試しになってしまった。しかし私はこわくはなかった。精確に言うと、こわいということがわからなかった。恐怖を感じられないほど幼かったということではない。私は平気だった。暗闇の奥に知らない誰かが潜んでいるかもしれないという今で言う「人怖」は多少はあったかもしれないが、そもそも他人が入り込むような土地ではない。人魂も何度か見たが、それも別にこわくなかった。お墓とは死んだ人たちが居る場所であることも承知していたが、幽霊が出る(かもしれない)という恐れや怯えを抱くことはなかった。私は「肝試し」に恐怖することはなかったし、かといってワクワクするわけでもなかった。つまりおそらく、それがどういうことなのか理解出来ていなかったのだ。
じゃあやっぱり幼かったからじゃないか、と言われそうだが、私は少年になり青年になり大人になってからも、肝試し的な場所ーーいわゆる心霊スポットなどーーは全然こわくない。わざわざ行ってみようとも行ってみたいとも思わないが、それは行く意味を感じていないからである。なのに「心霊スポット探索」みたいな動画コンテンツは大好きなのだ。これはどういうことなのだろうか?
と修辞的疑問を挟んでおいて、とりあえず話を先に進めると、私の父親はそんな土地で育ったので、暗所や墓地は日常の一部だった。私同様、私以上に、彼はそういうことはこわくなかったはずである。実際、これから話す出来事まで、私は父親が何かをこわがるさまを見たことがなかった。
ところが、である。小学校高学年になっていたと記憶するが、ある時、家族旅行で温泉のある観光地に行った。佐々木家が泊まった古めかしい大型ホテルには、昔はよくあったお化け屋敷がアミューズメントの一環として付属していた。私と父親は連れ立って、いかにもな雰囲気を醸し出すお化け屋敷を体験してみることにした(母親と妹は厭がって部屋に残った)。
だが、我々はお化け屋敷の入り口の前で、なぜだか立ち尽くし、父も子も、なかなか扉をくぐろうとしなかった。父親を見ると、その表情はこわばりつつも奇妙な微苦笑を浮かべている。あれ? お父さん、もしかしてこわがってない? すぐにピンときたのは他でもない。私もこわかったからだ。私はこわかった。我々は二人とも、まだ入ってもいないお化け屋敷がこわくてこわくてたまらなかった。というか、来たるべき恐怖の予感に脅えて立ち尽くしてしまっていた。親子して突っ立ったまま暫しの時間が過ぎ、やがて父親は息子にやや恥ずかしげに言った。「やめとくか?」 私がウンウンと頷いたのは言うまでもない。
私(たち)は、本物の墓地はこわくないのに、お化け屋敷はこわかったのだ。その後、私はお化け屋敷(的な施設)を体験することが何度かあったが、いつもこわい。すごくこわい。入る前からこわいし、出来れば入りたくない。だが有名な心霊スポットに行けと言われたら平気な顔で行って帰ってくるだろう。
私と似た感覚を持つひとは、結構多いのではないだろうか?
肝試しはこわくないのにお化け屋敷はこわい、という違いは、自分としては簡単に説明出来る。肝試しは「出ない」が、お化け屋敷は確実に「出る」からである。現実の体験である肝試しと、娯楽としてのお化け屋敷ならば、私は後者の方が断然こわい。だが当然、逆の人もいるだろう。お化け屋敷は何もかもが作りものだから全然こわくないが、心霊スポットはリアルだから(こそ)こわい、という。
こうして人間は二種類に分かれる。肝試しがこわいタイプとお化け屋敷がこわいタイプである。もちろん両方とも恐い人もいるだろうが。ひとまず簡単に言ってしまうなら、これは「現実」と「虚構」のどちらに「恐怖」を感じるか、ということになるだろう。
だが、この話は見かけほど単純なものではない。
いるものはいる
あるものはある。
これはいわゆるトートロジー(同語反復)である。あるものはあるに決まっている。「ある」から「ある」ということだが、この文は何も述べていないようでいて、あるものはあるのだからあるのである、という強調や、あるからあるんだよ!というような強弁の構えも感じられる。
これを、以下のように書き換えてみる。
いるものはいる。
文の意味自体は基本的には変わりはない。ただし「ある(在る)」が「いる(居る)」に置き換えられたことで、トートロジーの主体が事物から広義の生き物(「広義の」と言うのは人形や大仏やぬいぐるみなど実際には無生物であっても「居る」とすることがあるからである)に限定された。「居るものは居る」。裏返せば「居ないものは居ない」。それはそうだろう、とは思う。
では、これをこう変えてみよう。
居ないものは居る。
最初の「あるものはある」に当てはめてみると、これは「無いものは在る」になる。あからさまな矛盾、いわゆる撞着語法(オクシモロン)である。だが「無いものは在る」に比べると「居ないものは居る」はちょっとわかるというか、たとえば現実にはもう居ないのだが記憶の中には「居る」とか、実在はしていないが想像上は「居る」とかならば、言い方としては可能である。そもそも小説やマンガやアニメなど生身の人間を必要としない種類のフィクションは「居ないものは居る」をやっているのだとも言える。
では、先の文の助詞を変えてみよう。
居ないものが居る。
私の考えでは、ホラーの原理とはこれである。居ないはずのものが居た、ということではない。確かに居ないのに、居る。むろんこれもオクシモロンである。文意としては「居ないものは居る」と同じだし、その個別対象への適用とも言えるのだが、しかし「居ないものが居る」と言った/聞いた途端に、何やら怪しげな、生暖かい空気がたちこめてくるような気がする。闇が立ち上がってくるかのような気がしてくる。
だがしかし、居ないものは居ない、のである。それは居るものが居るのと同じくらい自明の真理であり、そのものが「居ない」ことに現実的な疑いを差し挟むことがない限り、単なる矛盾した言明でしかない。そして/しかし、私が思うに、ホラーという表現形式は、この「矛盾」を駆動因、いわば内燃機関にしており、最大限に利用している。
ここで肝試しとお化け屋敷に話を戻そう。私(と父親)が墓場をこわくないのは、そこには「お化け」は「居ない」と思っている(「知っている」と言ってもいい)からである。居ないものは居ないから居ない。だからこわくもなんともない。だがお化け屋敷は、その名の通り「お化け」が「居る」空間なのである。だからこそこわい。だって「居る」のだから。たとえ正体は薄給で雇われたアルバイトだったとしても、こちらをこわがらせるべくそこに待ち構えているのだから、こわいのだ。
ここで重要なことは、では要するに私は「お化けなどいない」と思っている(からこわくない)のか、ということである。私は「お化け」がいないとは思っていない。だが、いるとも思っていない。つまりわからない。細かく言うと、お化けでも幽霊でも心霊でも怪異でも呼称はとりあえずどれでもいいのだが、ともかくそう総称されるような存在(と言っていいのかもわからないが)の存在可能性のありなしということと、個別の「それ」の実在を信じるか否か、という二段階がある。幽霊の存在は否定し切れなくても、友だちが見たという幽霊の話は信じない、ということだってありえる。それでいうと私は、ひょっとしたら幽霊はいるのかもしれないし、心霊体験の類いも本当のことが含まれているのかもしれないが、そのような明確な体験を持ち合わせていない自分にはその真偽はわからないし、ある意味どうでもよい、ということになる。そしてここが肝心なのだが、もしも私自身が何らかの状況で「居ない(はずの)ものが居る」と確信しえたとしたら、それは「居るから居る」のである。もう「居ない」のに「居る」ではないのだ。
こうして話は「いるものはいる」に戻ってくる。それは最初の「あるものはある」というトートロジーに回帰するということでもある。ないならないし、あるならある。居ないなら居ないのだし、居るのなら居るのである。ただそれだけのことだ、と私はドライに考えている。そしてこれは心霊体験のみならず、他のあらゆるスーパーナチュラル(超自然的)な事象についても同じである。肝試しは「居ない」からこわくなく、お化け屋敷は「居る」からこわい。ただそれだけのことである。
しかし繰り返すが、それは私がスーパーナチュラルな存在を完全否定しているからではない。大昔から人類はパラダイムシフトが起こるまでは現在とは異なる種々の迷信を信じていた。あまりなさそうではあるが、この先の未来に、何かのきっかけで「霊界」みたいなものの実在が証明されることだって絶対にないとは言えない。だがもしもそうなったならば、それはもはや神秘ではなく、単に事実である。こわいこわくないではなく、ただそれはそこにあるのだ。
翻ると、つまりやはり「居ないのに居る」が、ひとに恐怖を抱かせるのだと思われる。何年も前に死んだ妻が隣の部屋に立っていたら、こわいと思う夫もいるだろう。だが彼は懐かしく嬉しいかもしれない。居ない妻が居ることをおそれつつも、同時に幸福を感じるかもしれない。しかしそれはこわくないということとも違う。こわいけれどこわくない。これもオクシモロンである。
心霊と妄想のあいだ
「居ないものが居る」は、厄介で困難な問題も発生させる。いわゆる「見える人」と「嘘つき」と「心を病んでいる人」の判別が付けられなくなる、という問題である。
たとえば、何人かで一緒にいて、その内のひとりが突然「あそこに誰かいる!」とか叫んで泣き出したとしよう。他の皆には誰も見えない。このとき、泣いている者は本当に霊を見たのか、皆を騙そうとしているのか、彼か彼女の妄想なのか、完全には確定出来ない場合がある。たとえひとりにしか見えていないのだとしても、何らかの理由でその人にだけ「見える」のだという可能性を100%排除し切れない。心霊的なものを全否定してしまうならともかく、そこにわずかでも留保を設けた瞬間に、この判別可能性は生じる。他愛のない(あるいは趣味の悪い)嘘であれば論外だが、実は幽霊が実在していて、ひとりだけがそれを視認する能力(?)を持っているのか、それとも幽霊はそこには居らず(これは必ずしも「幽霊」の全否定とイコールではない)、ただその人がそう思い込んでしまっているのか、果たしてどちらなのだろうか?
この問題はフィクションの中だと、より鮮明に、かつ複雑に浮かび上がってくる。とりあえず映画だとしよう。その場のひとりだけが「あそこに誰かいる!」と叫ぶ。このとき、その者が指差す「あそこ」に幽霊役の俳優が映っている場合と、そこには何もない場合とが考えられる。前者の場合は、この幽霊は居るのだな、と観客は思う。だがちょっと待て。今のショットは叫んだ者の「見た目」ではないか? だとするとそれは妄想かもしれない。逆に後者であっても、ひとりだけに見えているということの真実性は、ただそれだけでは完全否定は出来ない。誰も映っていないショットが、客観性のいかなる水準にあるのか必ずしも明確ではないからである。叫んだ者の視点ショットが省かれているだけなのかもしれない。現実世界なら私は私の視界で実在を(錯覚や妄想の可能性込みに)認識し判断するが、三人称と一人称が混在しえる(そして両者の区別が付かないこともある)映画の場合はそうはいかないのだ。
私が近年、機会を捉えて何度となく主張しているのは「小説は目に見えない」ということである。当たり前だ。だがこの当たり前さは掘り下げるに足る含蓄を有している。小説は言葉でしかない、文字でしかないので、いかに視覚的な描写がなされていたとしても、それは現実の光景とけっして完璧に一致することはない。そして小説は「見えない」ことを可能性に転化し、さまざまに利用している。
逆に言うと、映画は目に見える、見えてしまう。これも当たり前だが、映画の場合、観客の「見える」は作り手の「見せる」なのであって、つまりそこには「何を見せて何を見せないのか」という弁別の次元が介在してくる。特にホラー映画においては、この点は極めてクリティカルな問題を孕んでいる。先にも述べたように、やり方次第で物語内の超自然的存在の実在と不在の不確定性を導き出してしまうからである。そしてもちろん、このこと自体がホラー映画作家の腕の見せ所であり、才気才覚の評価基準になり得る。
映画に限らず、フィクションの内部では、何かが居るのか居ないのかは、究極的には宙吊りにされざるを得ないのではないかと思う。ジャンルや形式によってさまざまに差異はあるが、決定不能性を消去することは不可能なのである。であればこそ、たとえば「結局のところ幽霊が居たのか居ないのかわからないままで終わるホラー」であるとか、もっと言うなら「幽霊など居なかったのにすごくこわい話」さえ構想し得る。そしてそれらは全て、要するに「居るものは居る」と「居ないものは居ない」と「居ないものが居る」との三竦みによって成立しているのだ。
非在の信憑とポスト・トゥルース
「肝試しとお化け屋敷」と「居ないものが居る」、連続する二つの話によって、本論のアウトラインがほの見えてきたのではないかと思う。ここで連載タイトルの話をしておくと、私は「恐怖」の本質は「フィクション(虚構)」の本質と深いところで結びつき、絡み合っていると考えている。そしてそれは「恐怖」とは一種の「フィクション」なのではないか、という仮説も導出する。だから「恐怖というフィクション」なのである。恐怖とは虚構なのだ。こわさとは虚構の産物なのである
いや、これは現時点では、あくまでも「仮説」である。
というわけで、これから少し時間を掛けて、ホラーについて考えてゆきたいと思う。ジャンルとしては映画/映像/言語表現/視覚表現など多岐に渡ると思うが、ここまで述べてきたように、私の問題意識、関心の所在は、ホラー表現のジャンル論や歴史、様式美などトリヴィアルなところにはない。そもそも最初に記したように私はホラーファンでは全くないし、マニアックな知識も持ち合わせてはいない。しかるに私の議論は、あくまでも具体的なホラー表現に立脚しつつも、要所要所でかなり原理的な取り組みになることだろう。そしてそれは私が過去に著してきた多数の映画論や小説論、その他の批評群とも、さまざまな仕方で有機的に交錯してゆくことになろうかと思う。ホラーの原理とともに、フィクションの原理をも問い直す試みになれば、と願っている。
急いでもうひとつ重要なことを付け加えておきたい。原理とは言ったが、これも私がこれまでやってきた批評と同じく、これはアクチュアルな問いでもある。この連載は「今、ホラーを考える」ものであると同時に「なぜ今、ホラーなのか」を考えるものでもある。ここには二つの理由がある。第一に、2025年5月現在、日本は何度目かのホラーブームの最中にある、ということ。第二に、そのことが、おおよそここ10年ほどの間に日本のみならず全世界的に蔓延した、いわゆる「ポスト・トゥルース」的状況、ファクトとフェイクの混在と混乱とでも呼ぶべき事態と、どのように関わっているのか(そもそも関わっているのか)ということ。それはたとえば陰謀論とフィクションの関係性を考察することでもある。「ホラー化する日本」などというといかにも意味ありげだが、かつて映画の「Jホラー」が世界を席巻したように、なぜ日本では恐怖表現がジャンルを超えて独自の進化を遂げ、繰り返しホラーブームが訪れるのか、いま現在のブームは過去のそれとどう繋がっており、どこが異なるのか、こうした点についても、おいおい詳らかにしていきたい。
「ホラー=horror」の語源は、ラテン語の「horrere」である。意味は「毛が逆立つ、身震いする」。不意に背中を触られたらhorrereするかもしれないが、それは恐怖というより驚愕である。血や臓物を見せられたらhorrereするだろうが、それはコワいではなくグロいである。もちろんそれらだって「こわい」の一種ではあるのだが、そうやって他の語彙でも形容可能な感覚を引き算していって、次第に浮かび上がってくる、最後の最後にドロリと残る、得体の知れないhorrereこそがホラーの本質ではないか。それはつまり、理由がわからないのになぜか身震いを催し、全身が総毛立つ、ということである。
恐怖の現在と原理を、じっくりと探っていきたい。
(つづく)