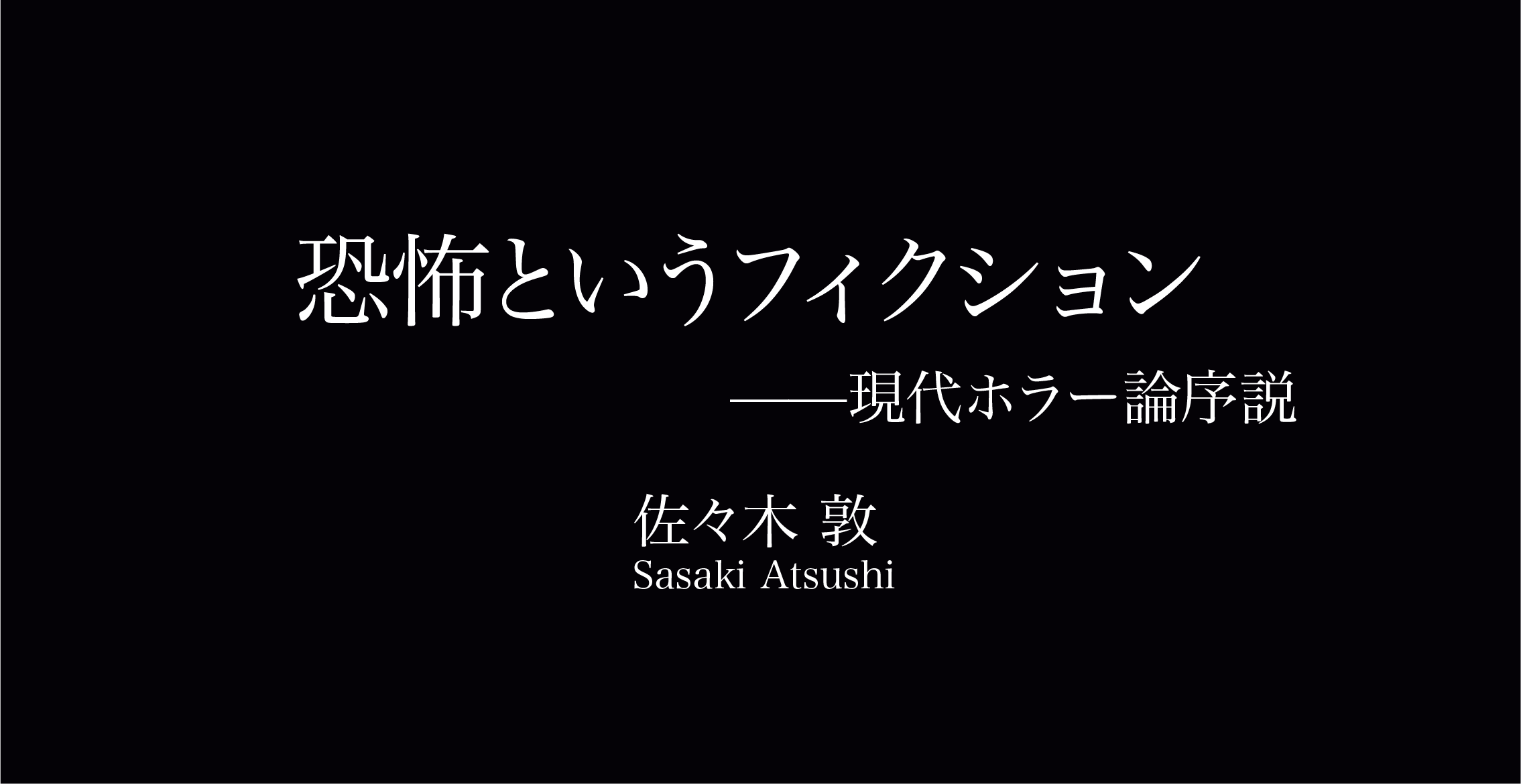佐々木敦さんによる「ホラー」をめぐる新連載が始まります。ひとはなぜ恐怖するのか、ひとはなぜ恐怖を必要とするのか、そもそも恐怖とは何か。わたしたちの普遍的な、しかしあまりにも個別的な情動を通じての、現代のフィクションをめぐる思索の旅。第2回は「Jホラー」なるものを決定づけた『リング』、その原作小説と映画化の周囲をめぐって展開されます。(*7月10日、本文の一部修正をおこないました)
Jホラーの誕生
Jホラーという言葉が誕生したのが正確にいつのことなのか、私は知らない。だが、それが1990年代以降であったことは確かである。JapanもしくはJapaneseの「J」を頭に付けるネーミングは、国鉄が民営化されて「JR」になった1987年以前にはほぼ存在していなかった。1988年にJ-WAVEが洋楽専門のFMラジオ放送局として開局し、そこで流される邦楽を「Jポップ」と呼ぶようになった(このことについては拙著『ニッポンの音楽』を参照)。日本たばこが「JT」になったのも同時期だし、農協が「JA」になったのが1992年、そして1993年のサッカー「Jリーグ」の開幕と、その人気爆発によって「Jナントカ」という呼称は大衆に行き渡った。1998年には河出書房新社の雑誌「文藝」のムックがきっかけとなって「J文学」ブームが起こる。おおよそ10年を掛けて「J」は一般化したわけである。
キャッチフレーズとしての「Jホラー」もまた、この流れに位置付けられるだろう。ホラー映画というジャンル名は80年代からあった(それ以前は恐怖映画とか心霊映画などと呼ばれていたと思う。ホラー=Horrorというワードはスティーヴン・キングが「モダン・ホラー」の旗手として日本でも話題になったあたりが始まりではないか?)。「日本のホラー映画」を「Jホラー」と言い換えることは宣伝戦略に過ぎないとも言えるが、現在は海外でもこの言葉は普通に使用されている(この点はJポップと似ている)。米英を中心に発展したホラー映画の日本におけるローカライズであるJホラーは、ひとつのブランドとして確立されていると言っても過言ではない。
そしてその発火点であり、今なおJホラーの金字塔とされるのが、1998年公開の『リング』であることは間違いない。Jホラーはこの作品から始まったとする歴史観もある(ということは「J文学」と同い年である)。鈴木光司原作、高橋洋脚本、中田秀夫監督。では『リング』とはいかなる映画だったのか?
それを観た者が一週間後に命を落とすという「呪いのビデオ」の噂が広まり、実際に死者が出始める。シングルマザーのTVディレクターである浅川玲子は興味を抱くが、呪いで死んだと思われる男女と自分の姪が同日同刻に亡くなっていた事実を知ったことをきっかけに取材を開始し、その流れで当のビデオを見る。更に幼い息子もビデオを見てしまう。彼女は息子を救うべく、別れた夫で物体に込められた思念を感受する特殊能力を持つ大学講師の高山とともに呪いの謎に分け入っていく。次第に明らかになるのは、非業の死を遂げた超能力者の山村貞子という女性の存在だった……以上が大まかなあらすじだが、多くの方はストーリーよりもクライマックスの「貞子」がテレビ受像機の中からにじり出て来るシーンでこの映画を記憶していることだろう。私もそうだ。物語的興味よりも映像の力によって「こわさ」を演出している。実際、シナリオの高橋洋と監督の中田秀夫は、原作の「小説」を大胆に換骨奪胎して一本の「映画」に仕立て上げている。
鈴木光司の小説『リング』では、主人公の浅川は男性の雑誌記者であり、呪いの調査の相棒となる高山は彼の高校時代の同級生という設定になっている。浅川がビデオを見せてしまうのは妻と息子である。最大の相違点は、山村貞子が呪いの発祥である点は映画と同じだが、小説では浅川と高山の調査の過程で彼女の存在が浮かび上がるものの、幽霊の姿では一度も登場しないということである。『リング』と言えばあのシーンと言っていいくらいなのに、実は映画にしか存在しない場面なのである。また、小説は映画よりも謎解き的な要素が強く、鈴木光司の原作も、もともとは広義のミステリの新人賞である横溝正史賞(現在の横溝正史ミステリ&ホラー大賞)の最終候補に残って書籍化されたものだった。鈴木の「オカルト・ミステリ小説」を中田と高橋が「(J)ホラー映画」に変換したというわけである。
小説『リング』から映画『リング』へ
小説『リング』が映画『リング』に「変換」されるプロセスは非常に興味深い。原作は鈴木光司のデビュー第二作であり(第一作『楽園』は日本ファンタジーノベル大賞優秀賞受賞作)、当時専業主夫をしながら小説を書いていた鈴木の、最新作『ユビキタス』にまで繋がる「父性」という最重要テーマがすでに見て取れる。『楽園』は今でいう「異世界ファンタジー」だったので「ホラー小説家」としての鈴木もこの作品で誕生したことになる。それはともかくとして、原作の出版は1991年、映画化より7年も前である。横溝賞の主催会社である角川書店(現KADOKAWA)から単行本で上梓された。以下、時系列順に本論と関係する事項を並べてみると、
1991年 単行本『リング』出版
1993年 角川ホラー文庫創刊 『リング』が最初の配本で文庫化される
1994年 日本ホラー小説大賞開設(主催は角川→KADOKAWA)
1995年 第二回日本ホラー小説大賞で瀬名秀明のデビュー作『パラサイト・イヴ』が大賞を受賞(第一回は大賞該当作なし)、大ベストセラーとなる
同年 鈴木光司「リング」シリーズ第二作『らせん』出版
1996年 映画『女優霊』(中田秀夫監督、高橋洋脚本)公開
1997年 映画『パラサイト・イヴ』公開(落合正幸監督)
1998年 映画『リング』および『らせん』(飯田譲治監督)が同時公開 大ヒット
同年 「リング」シリーズ第三作『ループ』出版
『リング』という作品と角川/KADOKAWAが、90年代の日本の「ホラー」をめぐる状況の変化に深く関わっていたということがよくわかる。創刊当初の角川ホラー文庫は、まだ日本ホラー小説大賞が存在していなかったので(現在は同賞の受賞作は作品によって文庫と単行本のいずれかで出版されている)、映画やドラマのノベライズや海外小説(ディーン・R・クーンツ『マンハッタン魔の北壁』やピーター・ストラウブの傑作『ココ』など)も出していた。文庫オリジナルもあったが角川書店と縁の深い赤川次郎や森村誠一などの人気作家のホラー的な作品もあった。
『リング』は単行本の時点ではさほど話題にならなかったようだが、文庫化によって大きく認知度を上げた。それは「ホラー」というジャンルにも言えたことだろう。そして『パラサイト・イヴ』という怪物的なベストセラーが登場したことで一挙に弾みがつき、『リング』『らせん』の同時映画化が実現する。両作の公開に合わせて鈴木光司はシリーズ第三作『ループ』を発表し、更に『エス』『タイド』、スピンアウト作『バースデイ』と「リング」サーガは続いていくことになる。
話を映画『リング』に戻そう。この作品が大ヒットを記録し、「Jホラー」の先駆けとされるようになった要因は一つではないが、原作から映画化までーーそれは1991年から1998年まで、90年代のほとんどを占めているーーの間に日本社会に起きた幾つかの変化が深く関係していると思われる。更に言うなら、鈴木光司が原作小説を執筆したのは1989年だったという。前述したようにこの小説は横溝正史賞(当時)への応募作であり、最終候補になった同賞の第10回は1990年度なので、当然それ以前に書かれていたわけだ。とすると、原作から映画までは、ほとんど10年の歳月が流れていたことになる。その間に何が変わったのか? ここでは二つのポイントについて述べておきたい。キーワードは「ビデオテープ」と「都市伝説」である。
映画は原作の「呪いのビデオ」の基本設定を踏襲しているが、小説が世に出た1990年前後と映画が公開された1998年では「ビデオ」という映像メディアの位置付けがかなり変わっている。小説で、死んだ四人の若者は皆で宿泊した貸し別荘の管理室でビデオを貸りて観たことが判明する。宿泊者へのサービスで話題作や人気作を並べている中にタイトル不明のビデオテープが存在し、不審に思った浅川はそれを観てしまうのである。このシーンは映画にもある。
いわゆる「レンタルビデオ」は1980年代にはすでに存在しており、それには家庭用ビデオデッキの普及という前提条件があったわけだが、初期のレンタルビデオ店はかなりグレーゾーンの業態が多かった。法整備と業界健全化が進むにつれて非合法の店は駆逐されていき、90年代前半には小規模なチェーン店もあったが、90年代後半に入るとTSUTAYAやGEOが大々的な全国チェーン展開を始める。業界第一位のGEOがフランチャイズ店舗の全国展開を開始したのが『リング』公開と同じ1998年であり、都市部ではTSUTAYAも店舗を急速に増やしていた。
映画にもビデオレンタルショップは出てこない。だが「呪いのビデオ」という都市伝説のリアリティは原作の刊行時より飛躍的に増していたのである。そして『リング』がビデオ化されると当然、GEOやTSUTAYAでレンタルされることになる。いわば『リング』のレンタルビデオ自体が「呪いのビデオ」的なニュアンスを帯びていくことになるわけだ。しかもVHSビデオというメディアは2000年代(ゼロ年代)に入るとDVDに取って変わられてしまう。レンタル用ソフトもVHSからDVDに急速に移行する。1998年という『リング』公開年は(結果として、ではあるが)極めて微妙で絶妙な時期だったことになる。現時点から見ると、貞子が出現する「呪いのビデオ」は、レンタルビデオの爛熟期とビデオカセットからビデオディスクへの転換期に位置していたことになるのだ。
「不幸の手紙」とインターネットの勃興
もう一点は「都市伝説」である。「観ると一週間後に死ぬ呪いのビデオ」は、誰でもわかるように、いわゆる「不幸の手紙」の変奏である。海外では「チェーンメール」と総称されている、何らかの仕掛けによって不特定多数の人間の間を受け渡されていく手紙の一種である。「○日以内に○人に同じ文面を送らないと不幸に遭う」というものだが、日本で流行ったのは1970年代半ば頃であり、それ以前から「幸運の手紙」が存在していた。「幸運の手紙」と言いながらも、それは「○日以内に○人に同じ文面を送れば幸運が訪れるが、送らないと不幸に遭う」というもので、要するに内容は同じである。ならばいっそわかりやすく「幸運」を「不幸」に反転させることでより明確に不安を煽り、人から人へと噂が伝播し、雑誌やテレビなどに取り上げられることで全国に拡散した。そのブーム(?)の火付け役のひとつが、つのだじろうの漫画『恐怖新聞』(1973年連載開始)だが、この作品については後で触れることにする。
「都市伝説」というワードは、民俗学者のジャン・ハロルド・ブルンヴァンが全米ベストセラーとなった著書『消えるヒッチハイカー』で提示した「Urban Legend」という概念の日本語訳である。この本の原著刊行は1981年だが、邦訳(大月隆寛他訳)は1988年に刊行されており、『リング』公開の前年に当たる1997年に新版が出ている。ブルンヴァンは同書で噂や口コミなどと呼ばれてきた現象のうち、特に都市型の民間伝承を「Urban Legend」と名付けることで理論化/定式化した。その直訳である「都市伝説」は『消えるヒッチハイカー』とともに日本に輸入されてきたわけだが、この語の使用は一部の好事家や雑誌などに留まっており、『リング』公開時も必ずしもまだ一般的ではなかったと思う。「都市伝説」が、この四文字ともどもブームになったのは、「Mr.都市伝説」とも呼ばれる芸人の関暁夫がテレビ番組で様々な都市伝説を披露し、最後に「信じるか信じないか、それはあなた次第」と言い放つのが大ウケしたゼロ年代半ば以降のことだろう。
小説にも映画にも「都市伝説」という言葉は出てこない。映画でも「噂」としか言っていないし、そもそも小説には「噂」という物語的要素がないのだ。だが、映画の「呪いのビデオ」は、こんにち言うところの「都市伝説」そのものである。
映画の最初の方に、松嶋菜々子演じる浅川玲子がテレビ局の同僚と「呪いのビデオ」を話題にしつつ「口裂け女」に触れるシーンがある(この場面は原作には存在しない)。「口裂け女」も有名な都市伝説だが、その流行は1970年代末である。『リング』以前の日本の有名都市伝説といえば、他に「ツチノコ」「人面犬」「トイレの花子さん」などが挙げられるだろう。重要な点は、こうした「噂」は口コミ以外は何らかの伝達手段(媒体)を必要とするということである。それは90年代半ばまでは郵便、電話、印刷物(新聞雑誌や書籍)、テレビラジオに限られていた。
ところが1990年代半ばにインターネットが登場する(それ以前もパソコン通信があったが限られた人しか使っていなかった)。俗に「インターネット元年」とも呼ばれる1995年の時点ではまだまだ一般的ではなかったが、90年代後半にネット環境は日進月歩で改善されていく。まだまだ回線速度は遅かったし、ブロードバンド(大容量通信)は実現しておらず、面倒なダイヤルアップで接続していたが、『リング』が公開された1998年には、ネットと電子メールは大衆に行き渡りつつあったのだ。
NTTドコモの携帯電話インターネット接続サービス「iモード」が開始されたのが1999年。同じ年に「インターネットオペラ」とも称された坂本龍一の『LIFE』が上演されている。あとの章で詳しく触れる「ネット=霊界」というアイデアを核とする黒沢清監督『回路』と、ネット掲示板を創作と宣伝に活用した岩井俊二監督『リリイ・シュシュのすべて』は、ともに2001年公開の映画である。「レンタルビデオ」と同じく、「都市伝説」にかんしても(映画にインターネットは出てこないが)、また『リング』という映画の感想や評判の伝播(=噂)という点でも、極めて微妙で絶妙なタイミングだったと言えるのではないだろうか?
『リング』『らせん』の映画公開と鈴木光司『ループ』刊行に合わせて出版されたムック『冒険者ガイド ループ界』に収録されているインタビューで、中田秀夫は「都市伝説」について、次のように述べている。
小説『リング』の呪いのビデオがうわさとして一人歩きしているらしいというのが出発点となりました。映画の中で語られますが、例えば口裂け女の伝承のように、発生源はたいへん不幸で、凄惨な事故、そこから人々の不安と期待を糧としながら恐怖の都市伝説は増殖と変容を重ねていく。リングビデオのうわさもそういうとらえ方です。小説『リング』ももともとは口コミでベストセラーになったと聞いてますが、映画も女子高生向けの試写会をして、私自身も彼女たちに、観て怖いと思ったら、1週間以内に他の人に是非観せるようにと、宣伝したりしました(笑)。
女子高生(に限らないが)の「噂」のプラットホームは、これ以後、固定電話と教室のお喋りからケータイとメールに移っていく。ビデオテープがDVDに変わるのと並行して、ゼロ年代の半ばまでに「都市伝説」のインフラはネットに完全に移行している。「不幸の手紙」が「呪いのビデオ」になり、そして「呪いのメール」や「呪いのDVD」になる(更に「呪いのブルーレイ」「呪いのダウンロード」「呪いのストリーミング」etc..).。「ホラー/恐怖」とメディア/テクノロジーの進化/変化は切っても切り離せない。
「ビデオ」と「都市伝説」から見えてくるのは、『リング』の一種独特とも言えるピンポイント的な時代性である。1998年という公開年の微妙さと絶妙さは、この映画の設定や意匠を、あっという間に時代遅れにしてしまった。にもかかわらず、いや、むしろそれゆえにこそ、この映画は「過去→現在→未来」と進む時間軸から解き放たれて、独自の魅力と持続性を有することになったのではないか?
敢えて言うなら、要するに『リング』はいかなる意味でも「新しく」はなかった。「新しく」あろうともしていない。鈴木光司の原作執筆時から数えると、ほぼ十年の時を経た映画化でありながら、中田秀夫と高橋洋は『リング』を1998年にふさわしいアップトゥデートな作品に更新しようとはしていない。彼らがしたのは、おそろしいスピードでメディア環境が変容していく90年代の終わりがけに、すぐ時代遅れになってしまいかねない最新モードを目指さないこと、むしろその時点の「今」に流れ着いた過去の時間の堆積を『リング』という一本の映画に封じ込めようとすることだったのだ。
そして、この「堆積」の結晶体、「過去」の象徴が「貞子」だったのである。原作には存在しない、井戸から上がってきた貞子がテレビのブラウン管(これもこの後すぐに時代遅れになってしまった)から拔け出てくるあの恐怖の場面は、まずもって「90年代」というメディア/テクノロジーの激動のディケイドーー特にその半ばに位置するインターネットの登場は不可逆的な変化を齎したーーへのアナクロニズム的な一撃であり、更にはそれ以前のはるか昔ーー霊が霊であり、怪異が怪異であり、怨みが怨みであった古き良き時代ーーから「今」へやってきたタイムマシンでもあったのだ。その結果、物語の最初から死んでいる「貞子」は永遠の命を得ることになったのである。
『リング』が現在に結びつけるもの
映画『リング』の正規の続編は同時公開された『らせん』(監督の飯田譲治が脚本も担当)であるわけだが、その後、第一作と同じ中田秀夫×高橋洋コンビによってパラレルワールド的な続編『リング2』(1999年)が製作された。これは鈴木光司の「リング・サーガ」とはまったく別のオリジナル・ストーリーになっている。2000年には、鶴田法男監督、高橋洋脚本による、鈴木の『バースデイ』中の短編を原案とする『リング0 バースデイ』が公開された。そしてそれから10年以上が経った2010年代になってから『貞子3D』(2012年、英勉監督)に始まる一連の「シン貞子もの」が始まるものの、(鈴木光司はさまざまなかたちで関わっており、2019年の『貞子』は中田秀夫が監督しているが)ここではこれ以上触れない。触れておくべきは『リング』のハリウッド・リメイクである『ザ・リング』のことである。
のちに「パイレーツ・オブ・カリビアン」シリーズでヒットメイカーとなるゴア・ヴァービンスキー監督による2002年のアメリカ映画『ザ・リング』は、舞台をシアトルに移し、登場人物がアメリカ人であること以外は、設定も展開も、映画『リング』をほぼそのまま踏襲した作品となっている。ハリウッドによる現代日本映画のリメイク自体が珍しかったわけだが、『ザ・リング』は批評的にも好評で、興行的にも全米でヒットを記録した。これは明らかに「ほぼそのまま」が功を奏したということだろう。その結果、続編『ザ・リング2』(2005年)は中田秀夫がメガホンを握ることになった。中田はこれがハリウッド・デビューだった。この起用がのちに『呪怨』の監督、清水崇のハリウッド進出に繋がることになる。『ザ・リング』と同じアーレン・クルーガーによる『ザ・リング2』のシナリオは『らせん』とも『リング2』とも異なった物語になっている。そして、やはりというべきか、2017年にはシリーズ第三作『ザ・リング/リバース』が製作されたが(監督はF・ハビエル・グティエレス)、この時点でオリジナルとはかけ離れた世界観の作品になってしまった。よくある話ではあるが。
ともあれ、『ザ・リング』の成功は、日本製ホラー映画、ジャパニーズ・ホラーのユニークネスを世界に知らしめることになった。いったい何がウケたのだろうか? もちろん例の出現シーンは『ザ・リング』にもある(こちらの名前は「サマラ」)。オリジナルと同様、その映像的なインパクトは大きかっただろう。だがそれだけではあるまい。「ビデオテープ」と「噂=都市伝説」が、やはり効いていると思われる。だが、もっとも大きかったのは、すべての物語の始まりである「貞子(サマラ)」の存在だ。彼女はホラー映画史上に残る究極の悲劇のヒロインであり、後続のホラー作家たちに与えた影響ははかり知れない。だが、この点については章をあらためて論じたいと思う。
映画『リング』が「Jホラー」の嚆矢と言えるのは、その斬新さや完成度のみによるのではない。もちろん、それ以前の数多の「ホラー映画」とは一線を画す目覚ましい傑作であることは間違いないのだが、その存在意義は何よりも、内外の「ホラー映画」の歴史を或る独特な仕方で凝縮し、映画という表現形式(テクノロジー)が持ち得る「恐怖」の本質を鮮やかに明示し得た点にある。この意味で『リング』は疑いなく「Jホラー」を創始したと言ってよい。この映画は、それ「以前」と「以後」に挟み撃ちされたーーピンポイントの、微妙で絶妙なーー現在形の作品なのであり、であるがゆえに古びることがない。
だが、こんにち言うところの「Jホラー」が創始されるためには、『リング』だけでは足りなかった。少なくとももう一つ、重要な歴史的条件が必要だった。黒沢清という固有名詞がそれである。
(つづく)