一九七七年四月十七日 日曜日
教会へ行き、ひざまずいてもっと儲かるように祈っていると、ショッピングバッグ・レディがやってきて金をせびられた。五ドルくれといい、いや十ドルだという。まるでヴィヴァみたいだ。五セント硬貨をやった。すると、女はぼくのポケットに手を突っ込むんだ。
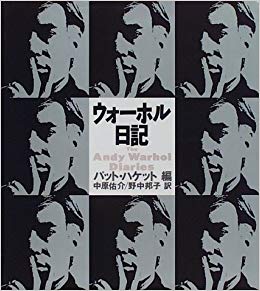
パット・ハケット編『ウォーホル日記』(中原佑介・野中邦子訳/文藝春秋/一九九五年)
あなたはアンディ・ウォーホルという名前からどんな作品を思い浮かべるだろうか。シルクスクリーンでキャンベル・スープ缶やマリリン・モンローを描いたポップ・アートだろうか? 監督した『チェルシー・ガールズ』、『エンパイア』、『スリープ』といった前衛映画だろうか? それともプロデュースしたロックの名盤『ヴェルヴェット・アンダーグラウンド&ニコ』だろうか? そのすべてが今や古典だ。
ウォーホルはありとあらゆるジャンルに手を染めたマルチメディア・アーティストだった。絵画、映画、音楽だけに留まらず、雑誌『Interview』を創刊し、日本のTVCMにまで出演している。しかし、文学を専門とする私にとって、ウォーホルはいつだって作家だった。
少なくとも日本で、ウォーホルの著作は彼が手がけた他のジャンルよりは高く評価されていないようだ。だが、日本でも翻訳された『ぼくの哲学』(落石八月月訳/新潮社/一九九八)、『ポッピズム ウォーホルの60年代』(パット・ハケット共著/文遊社/二〇一一)、『ウォーホル日記』の三冊は、海外では古典的な名著しか収録しないことで知られるペンギン・モダン・クラシックスから出版されている。英語圏では文筆家としてのウォーホルの評価は他のジャンルに負けず劣らず高い。
ウォーホルは作家としてのキャリアを小説から始めた。一九六八年に出版された『小説a』(未邦訳)は、ウォーホルと彼のスタジオであるファクトリーの常連だったヤク中のオンディーヌが、ニューヨークを散歩しながら交わしたとりとめもないお喋りを録音し、文字起こししたもの。ロクな編集作業も行わずに出版したため、当時、批評家からはすこぶる評判が悪かった。しかし、現在も新刊で入手できることからわかるとおり、今ではこの小説もそれなりの評価を勝ち得たと言っていい。
ウォーホルの著作が優れたものとなるのは、ファクトリーにパット・ハケットという女子大生がタイピストとして勤務するようになってからだ。ハケットはその若さにもかかわらず、素晴らしい編集者だった。ハケットとの共同作業は『ぼくの哲学』から始まり、『ポッピズム ウォーホルの60年代』、ウォーホルの死後に出版された『ウォーホル日記』まで続く。この三冊を作るにあたってウォーホルはまったく「手を動かして」書いてはいない。そのすべてはウォーホルが口頭で喋ったものをハケットがタイプし、編集を加えたものだ。
『ぼくの哲学』はウォーホルの機知に富んだ、ユーモアたっぷりの箴言が満載の楽しい本だ。『ポッピズム ウォーホルの60年代』はイーディ・セジウィックとの関係(イーディ・セジウィックの生涯についてはジーン・スタインとジョージ・プリンプトンの共著『イーディ―’60年代のヒロイン』〔筑摩書房/一九九八〕に詳しい)とヴァレリー・ソラナスによるウォーホル銃撃事件(『I SHOT ANDY WARHOL /アンディ・ウォーホルを撃った女』として映画化された)を主軸に、カウンターカルチャーが花盛りを迎えた狂乱の一九六〇年代をノスタルジックに、だが冷静に振り返った見事な回想録。そして、作家としてのウォーホルの代表作がこの『ウォーホル日記』である。
『ウォーホル日記』はウォーホルが前日に起きたことを電話でハケットに報告し、それをハケットがタイプした二万ページに及ぶ草稿を元に編集したものだ。日記は一九七六年十一月二十四日水曜日から始まり、ウォーホルが亡くなる五日前の一九八七年二月十七日火曜日で終わっている。
アメリカは好景気に沸き、ヤッピーと呼ばれるエリートビジネスマンの若者たちがニューヨークを闊歩していた。その代表格が不動産王で現在の大統領、ドナルド・トランプだ。トランプは『ウォーホル日記』にも一九八一年四月二十四日火曜日から登場する。ブレット・イーストン・エリスの小説『アメリカン・サイコ』は、この時代を舞台にトランプに憧れるヤッピーの殺人鬼を主人公とした物語だ。
『ウォーホル日記』のページを開いた瞬間、読者は氾濫する夥しい著名人の名前に驚くだろう。俳優ではジョディ・フォスター、エリザベス・テイラー、シルベスター・スタローン、リチャード・ギア。ミュージシャンではルー・リード、ライザ・ミネリ、ジョン・レノン、ミック・ジャガー、マイケル・ジャクソン、カルチャー・クラブのヴォーカル、ボーイ・ジョージ。デザイナーのホルストンにケネディ大統領夫人ジャクリーン・ケネディ・オナシス。作家ではトルーマン・カポーティ、ウィリアム・バロウズたちが姿を現す。
ウォーホルは子供の頃に映画に夢中になって以来、自分自身がアメリカを代表する有名人になってからもなおミーハーだった。日記には毎夜のようにウォーホルが出席したというパーティの記述が頻出するが、彼のミーハーぶりはそこで出くわしたスターにサインをねだるほどだった。そうした箇所に目を奪われた読者は、『ウォーホル日記』をゴシップ満載の軽佻浮薄な本と短絡的に捉えがちだ。しかし、スノッブな記述に惑わされず、『ウォーホル日記』をしっかりと読み込めば、彼の素顔が浮かび上がってくる。
日記の前半でウォーホルは、アルコール中毒とドラッグ中毒に苦しみ、書けなくなったトルーマン・カポーティを立ち直らせようと悪戦苦闘している。若き日のウォーホルはカポーティのストーカーだった。「ハッピー・マンデー」、「ハッピー・チューズデー」、「ハッピー・ウェンズデー」と書いた葉書を毎日カポーティの家の郵便箱に投函して嫌がられ、最後にはカポーティの母親に「息子に近寄るな」と言い渡されるほどだった。ウォーホルは酒と薬に溺れるカポーティにうんざりして愚痴を零しながらも励まし続け、自らの雑誌『Interview』に作品を書かせる。ウォーホルが書かせた短編小説とエッセイをまとめたものが、カポーティ最後の著作『カメレオンのための音楽』となった。
ウォーホルは文学に関しても確固とした批評眼を持ち、辛辣で容赦がない。ウォーホルにはウィリアム・バロウズとの共著『バロウズ/ウォーホルテープ』(ヴィクター・ボクリス、ウィリアム・バロウズ、アンディ・ウォーホル著/山形浩生訳/スペースシャワーネットワーク/二〇一四年)があるが、この本の原型となった対談をこなしている間に、バロウズを日記でこき下ろしている。「ぼくにいわせれば、彼は一流の作家ではない。つまり、彼は傑作『裸のランチ』を一つ書いたけど、いまや過去にすがって生きているようなものだ」(「一九八〇年三月一日 土曜日」)。
日記の後半でウォーホルは、ドラッグで身を持ち崩し、女性関係にもだらしがない後輩の画家ジャン=ミシェル・バスキアになんとか絵を描かせようとしている。助力の甲斐なくバスキアは孤立していき、ウォーホルの死の翌年、後を追うようにヘロインのオーバードーズで死ぬ。日記に書かれた二人の関係は、デヴィッド・ボウイがウォーホル役を演じた映画『バスキア』でも描かれている。カポーティやバスキアとの関係からわかるとおり、ウォーホルは才能ある芸術家には面倒見が良く、優しい。
ウォーホルはフラットでクールな作風で知られ、マスメディアに登場する時は恐ろしく寡黙で、何を考えているかわからない人間というイメージが強かった。だが、この日記でのウォーホルはとてもお喋りで、知的で、ユーモラスだ。ナイーヴといっていいほど繊細であり、かわいらしい。毎日しっかり仕事をこなし、日曜日には必ず教会に通い、貧しい人のためのボランティアに精を出す真面目な一面もある。
自分を銃撃したヴァレリー・ソラナスの脅迫電話に怯え、当時ゲイの間に大流行したエイズに恐れおののき、一九八〇年に出会った既婚の映画プロデューサー、ジョン・グールド(ウォーホルの亡くなる一年前にエイズで死亡している)との恋に悩む、人間味溢れる孤独な寂しがり屋でもある。
「ジョン[・グールド]はいったいどうしているんだろう。状況の発展がまったくないからね。でも、ぼくは恋をしていなければだめなんだ。さもなければ、気が変になってしまう。何かを感じていたいんだ」(「一九八一年七月六日 月曜日」)。これほどまでにウォーホルが真情を吐露した作品がほかにあるだろうか。
『ウォーホル日記』は一九七〇年代半ばから一九八〇年代半ばまでのアメリカ社会を活写した優れた日記であるのみならず、「人間ウォーホル」を彼のどの作品よりも真摯に伝えている記録文学の傑作だ。アンディ・ウォーホルは二十世紀後半を代表する画家であるだけではなく、間違いなく二十世紀後半を代表する作家である。
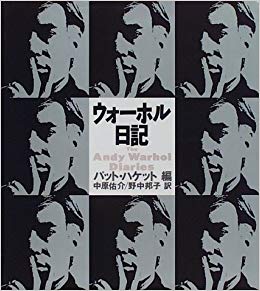
パット・ハケット編『ウォーホル日記』(中原佑介・野中邦子訳/文藝春秋/一九九五年)
バナー&プロフィールイラスト=岡田成生 http://shigeookada.tumblr.com

