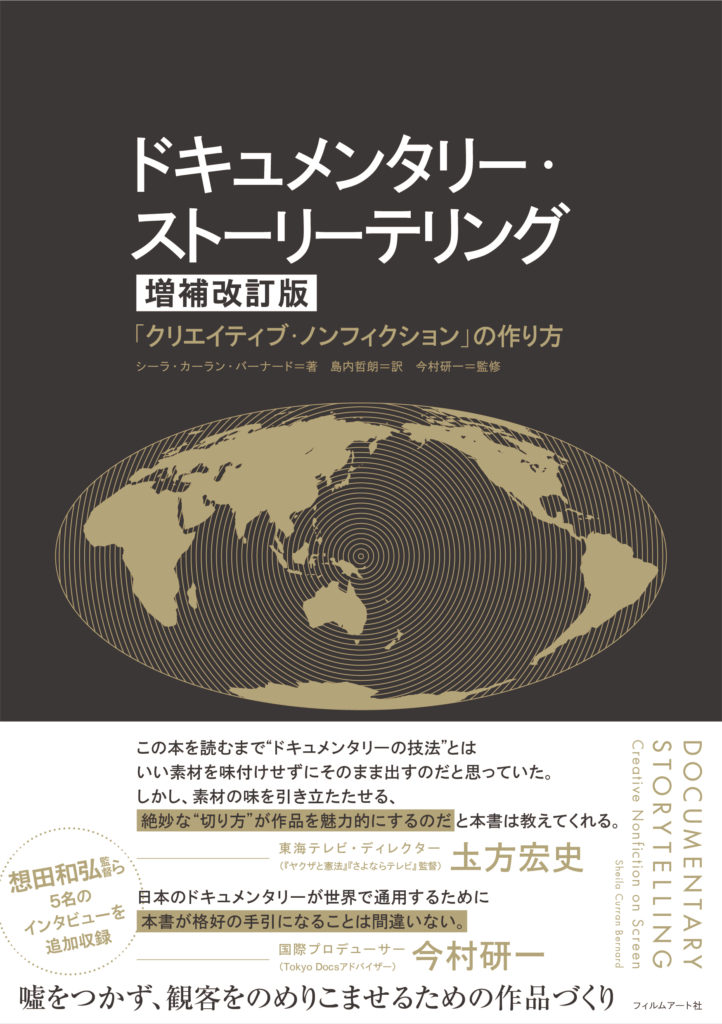2020年10月24日発売『ドキュメンタリー・ストーリーテリング[増補改訂版] 「クリエイティブ・ノンフィクション」の作り方』。ドキュメンタリーやノンフィクションの作品作りに必要な知識が詰まった1冊です。今回の増補改訂版の刊行にあたり、2014年刊行の旧版を愛用されている圡方宏史さん (東海テレビ・ディレクター、『ヤクザと憲法』『さよならテレビ』ほか、以下 圡方)、佐々木健一さん(NHKエデュケーショナル・ディレクター『ブレイブ 勇敢なる者』シリーズ、『ボクの自学ノート』ほか、以下 佐々木)のお二方に、本書の魅力や、現場から見た日本のドキュメンタリー制作の現状を語っていただきました。
「『さよならテレビ』はこの本があったおかげで
できたと言っても過言ではないです」
──最初に、お二人のドキュメンタリーとの関わりについてうかがえればと思います。関心をもったきっかけや、影響を受けた作品、実際に制作に携わられたときのことなどを教えてください。
【佐々木】学生時代、原一男の『ゆきゆきて、神軍』(1987年)を初めて見て、衝撃を受けたのが印象深いです。基本的に映画と言えばスピルバーグとかそういうエンタメ作品ばかり見ていたのですが(笑)、大学の図書館で借りて見て……まあ、びっくらこいて。緊迫感あるシーンの連続で、ドキュメンタリーに対するイメージが崩れました。当時、ちょうど原さんが早稲田大学に講師として来られていたので、その授業に一瞬だけ潜ったりして、それから自分でもドキュメンタリー映画制作の真似事みたいなことを始めたんです。就職もドキュメンタリーを作る方向に行きたいなぁと漠然と考えるようになって、今の会社に入りました。でも、実際には主に教育系の番組を作る会社だったんですが…。
それから入社1か月後ぐらいに、当時NHKのハイビジョン特集の枠で放送された池谷薫さんの『延安の娘』(2002年)というドキュメンタリーを見たんです。この作品は、逆光の中を列車が走ってくる映画みたいなシーンから始まるんです。ナレーションも一切ない。『ゆきゆきて、神軍』みたいな作品はテレビ業界では作れないと思っていたら、「すごい番組を作ってる人もいるんだ!」と知って、衝撃を受けました。一方で、その頃の自分は入社したてなので、料理番組とかを制作しているんですよ。「こんな番組、いつになったら作れるようになるんだろう?」なんて思っていました。
今の自分に最も影響を与えている作品は、アリ・フォルマン監督の『戦場でワルツを』(2008年)。『ゆきゆきて、神軍』や『延安の娘』は、いわゆる“みんながよくイメージするドキュメンタリー作品”だと思います。取材対象に密着して撮るスタイルです。でも、『戦場でワルツを』はほぼ全編CGアニメーションでできていて、それでも歴としたドキュメンタリー作品であるということに強い衝撃を受けました。
『戦場でワルツを』と『ドキュメンタリー・ストーリーテリング』という本に出会ったのが、ちょうど「自分らしいスタイルは何だろう?」と思い悩んでいた時でした。この本には、自分がドキュメンタリー制作に対して疑問に感じていたことや違和感がそのまま書かれてあった。入社してもう10年ほど経っていて、その頃、すでに他の制作者と一味違うドキュメンタリー番組も作り始めていたんですけど、「変化球だね」なんて言われたりしていたんです。でも、世界に視野を広げれば、何も不思議なことではないということを知った。なので、この本にはものすごくお世話になりました(笑)。
たとえば、エイズ治療薬を世界で初めて発見して、毎年ノーベル賞候補に挙げられる満屋裕明(みつや・ひろあき)さんのドキュメンタリー番組を2015年に作っているのですが、この作品は自分の中ではものすごく大きな一本だったんです。実写のドキュメンタリーシーンに加えて、豊富なCGアニメで構成した番組です。満屋さんは月の半分をワシントン郊外で過ごしているのですが、向かう飛行機の中にもこの本を持ち込んで読んだのを覚えています。こんな分厚い本をわざわざ(笑)。


『Dr.MITSUYA 世界初のエイズ治療薬を発見した男』©NHK
【圡方】佐々木さんがこの本に会ってなかったら、僕もこの本を紹介してもらうこともなかったですし。だからそういう意味ではすごい感謝してます。何の時に僕には教えてもらったんでしたっけ?
【佐々木】まだ、『さよならテレビ』(2018年テレビ放送/2020年劇場公開)を撮影してる時ですよ。
【圡方】ああ。すごい時に教えてもらったんだ。ちょうどその時『さよならテレビ』の取材の最中で。取材は1年7か月やったんですけど、1年が経って、素材が集まってきたものの、それをどうしていいかわからなくて途方に暮れていたんです。これまでの作品は比較的短い期間で仕上げて、ある程度構成を考えながら撮っていくかたちでした。ただ、そんな方針もなく1年とりあえず撮っちゃった後で、これは困ったぞと。どうしたらいいんだろうって思った時に、なんとなく佐々木さんがピンと頭に浮かんで。とりあえず悩み相談をしに行ったんです。具体的なことも何もなく、駆け込み寺みたいな感じで(笑)。
【佐々木】急に渋谷に来るって「何が目的だろう?」と怖かったですよ、最初(笑)。
【圡方】そのとき佐々木さんから教わったなかで、一番心に刻まれてるのが三幕構成ですね。そういうことを考えてドキュメンタリーを制作している人ってめちゃくちゃ少ないんです。少なくとも自分の会社にはいない。だから、なかなかそういう相談もできなくて。佐々木さんだったらなんかこの悩みに何かヒントをくれるんじゃないかって、もう藁をも掴む思いで行ったんですよ、東京に。
【佐々木】圡方さんって、すごく素直な方ですよね。もし、映画業界の人が「三幕構成って何?」って聞いたら笑われるじゃないですか。「そんなことも知らねえのかよ」って。あの頃、僕はネットのコラムなどでよく三幕構成のことを書いていたんですけど、テレビ業界の人から「え? そんなのがあるの?」なんてよく言われました。構成の基本も知らないテレビマンって少なくないと思いますよ。
【圡方】たぶん佐々木さんはある程度ドキュメンタリーが好きでNHKエデュケーショナルに入られたと思いますが、僕は全然知らずにいわゆる情報番組を、会社に入って5、6年やってたんです。まったくドキュメンタリーというものを知らなかったし、ドキュメンタリーをやってる人たちのこともちょっと避けて通っていたくらいです。
ドキュメンタリーを始めたきっかけは、入社10年目くらいで報道部に異動になったタイミングです。そのときは『約束 名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の生涯』(2013年)という、仲代達矢さんと樹木希林さんで映画化された作品の助監督に駆り出されてたんですね。入社1年目のころに昼ドラで助監督の経験があったので。それで現場にいたら、ロケバスの中で「お前今何やってんだ」って阿武野さん(東海テレビ プロデューサー)に話しかけられて。そのときは「ルーキーズ」というNPO法人が高校野球を辞めてドロップアウトした子たちを集めて野球を教えてるっていう10分ぐらいのニュースの企画をやってて、その話をしました。そうしたら「じゃあちょっとそれをドキュメンタリーにしてみろ」と言われて無茶苦茶なノリでドキュメンタリーをやることになりました。それが『ホームレス理事長 退学球児再生計画』(2013年)になるんですけど。
そうやってドキュメンタリーをやることになったので、今でも完全に両足を突っ込んでる感覚はまったくないんです。ドキュメンタリストという言葉に対してのくすぐったさもありますし。ましてやドキュメンタリーの「構成」なんていうのは……一昨年ぐらいに佐々木さんから聞いて初めて知ったんです。なので『さよならテレビ』はこの本があったおかげでできたと言っても過言ではないです。
それまでの作品は偶然の産物みたいな感じで過去の経験とか編集マンの力とか借りながら作ってきましたけど、『さよならテレビ』で初めてちゃんとした構成を作って、ここが第二幕と三幕の間なんだというのを逆に編集マンに「ちょっと騙されたと思ってこれでやってくれ」っていうふうに言って作りました。
『さよならテレビ』予告編
“持続可能な”ドキュメンタリーの方法論
──さっそく本のお話もしていただいて、ありがとうございます。お二人の出自がそれぞれ違うのは興味深いですね。その後業界の内側に入ってドキュメンタリーをどんどん作っていくなかでどのようなことを感じられたのでしょうか。
【佐々木】圡方さんはほぼ無菌状態でドキュメンタリー制作を始められたから「え、これってめちゃくちゃ偏った世界じゃん!」とか「どうして、こんなに狭いスタイルなの?」って、普通に疑問や違和感を覚えたと思うんですけど。
【圡方】ありましたね。
【佐々木】「ドキュメンタリーは、現実をありのままに映すものである」なんて思い込んでいる人からすると、この本に書いてあることはなかなかスッとは理解できないんじゃないかなと思います。この本の巻末で著者が多くのドキュメンタリストと対談していますが、とにかく「ストーリーテリング」の話を聞いていて、この本が説いているのは「ドキュメンタリーも、ストーリーを紡ぐ方法論が最も持続可能な作り方だ」ということなんですよね。
でも、ドキュメンタリーって、何の準備もせずになんとなく撮りまくって、そのうち何か面白いことがカメラの前で起こって、それを編集して、それがリアルなものとして伝えられる、というイメージが強いんですよね。先ほど圡方さんが「1年間撮影していた」って言ったじゃないですか。だけど、そもそも1年間撮影を続けることなんてできないですよ、普通は。
【圡方】そうですね。たしかに。
【佐々木】撮影素材はものすごく膨大になるし、編集期間も延びて、とんでもない経費がかかる。だから、若い時に自分が衝撃を受けたようなドキュメンタリーを継続的に作ることはほぼ不可能であるという現実にぶつかるんですね。だからこそ、僕はこの本が説く方法論に賛同しているんです。“持続可能な”ドキュメンタリー制作のスタイルについて書かれているので。
これは結構、大事な話だと思います。僕が大学生の頃に日本のドキュメンタリー界で尊敬を集めていた方々のスタイルを実践しようとすると、作品を継続的に制作することはきわめて困難なのです。収益性に限界があるし、1つの作品を作るのにものすごく時間がかかる。「とりあえずたくさん撮る」というスタイルだと、編集期間も長くなる。ミキサーも雇えずに自分で音声をミキシングすることになる。編集も自ら行うしかないので、複雑で高度な編集は難しく、必然的にシンプルなカット編集のスタイルになる。CGやアニメーションと融合させるような演出も行えない。つまり、選択肢が限られて、制作スタイルが固定化しちゃうんです。また、こうしたスタイルでドキュメンタリーを制作する人は、自分と身近な接点があるものから取材対象やテーマを選びがちになる。でも、それを続けるとだんだんネタも枯渇していきますよね。だから、よく皆がイメージするドキュメンタリー制作のスタイルって、続けていくのは相当苦しいと思うんです。
あまりちゃんと理解されていないんですが、テレビ・ドキュメンタリーの世界では東海テレビだけが異常に恵まれた条件と環境が与えられているんですよ。きわめて特例だと思います。珍しく特権的に長期ロケ、長期編集ができる。だけど、他の局ではなかなかそんなこと、認めてもらえないんです。だから、せいぜい1か月ほどの限られたロケ期間の中で、どうやったら良質なドキュメンタリーを制作できるのか、考え抜いた結果が自分の今のスタイルで、それがまさにこの本に書いてある方法論と一致したんです。ドキュメンタリー制作に対するいろんな自分の違和感や疑問に対して、この本が答えてくれたような気がしました。
それから、この本に載っている作品をどんどん見るようになると、世間には知られていない、すごくいい作品が山ほど見つかって。特に僕は、ジェームズ・マーシュ監督の『プロジェクト・ニム』(2011年)という作品がすごく好きです。チンパンジーを人間の子どものように育てた実験の顛末を題材にした作品です。
『プロジェクト・ニム』予告編
【圡方】ああ、見てない。
【佐々木】この作品は、簡単には見られないんですよ。日本では、東京国際映画祭で1回上映されただけで、WOWOWで1回放送されただけなので。『プロジェクト・ニム』にはものすごく影響を受けました。作り方、インタビューの撮り方など。今回、読み直した中で改めて感心したのが、ジェームズ・マーシュ監督はインタビューをものすごく重視していて、「取材相手への質問を考えるのに丸1日かける」と巻末の対談で発言しているんです。実は、自分も似たようなことをしていて、どんな質問をどういう順番で投げかけるか、事前に作成したロケ・スケジュールにまで書き込んでいるんです。
【圡方】すごい。初めて聞きました。
【佐々木】もちろん、その通りに質問することが目的ではなくて、そういう準備をして撮影に臨むことが重要だということ。カメラマンも事前にそれを見ているので、「この質問が本丸。ここ、攻めるよ」という時になったらスイッチが入って、その瞬間に勝負をかける。インタビューも、1回きりのドキュメンタリーですからね。だから、欧米のドキュメンタリーはものすごくインタビューを重視する。実際に制作している人間なら分かると思いますが、質問の仕方や撮影状況の作り方によってインタビューの出来って全然変わりますからね。だから、インタビューにそれだけの準備をして臨むのは当然のことなんです。
でも、不思議なのが、日本のドキュメンタリーってなぜか「インタビューは簡単に、安易に撮れるものだ」と思い込んでいたりしません? パっと現場に行って、必要なインタビューだけ撮って、前後はナレーションでつなげばいい、みたいな。そういうお手軽なインタビューと、撮影も内容も高度でエモーショナルなインタビューって、雲泥の差なんですよ。インタビューという手法自体にドキュメンタリストとしての高度な技術が必要なのに、そこをなぜか軽視する風潮が日本のドキュメンタリー界には少なからず存在すると思います。本当、不思議ですよ。だから、自分はそこを徹底的に見直そうと思って、インタビューを軸に構成するスタイルを追求していったんです。リアルな現在進行形を追いかけてなくても、過去を回想するスタイルでも見るべき作品は作れるはずだし、ドキュメンタリーの話法や技術、理論によってそれは可能だ、と。
構成抜きでドキュメンタリーは考えられない
──ロケ期間は1ヶ月ほどとおっしゃってましたが、編集も含めるとテレビ・ドキュメンタリーの場合だいたいどのくらいの期間でひとつの作品を作ることが多いのでしょうか。
【佐々木】通常は、ドキュメンタリーの特集番組でもせいぜい3、4ヶ月の期間だと思います。例えば、去年制作したBS1スペシャル『ボクの自学ノート~7年間の小さな大冒険~』(2019年)の撮影期間は10日ちょっとしかありませんでした。そうしないと、CGアニメなどに予算を割けないんです。撮影期間を絞った分、編集は多めに1か月ちょっと取りました。こうやって毎回、なんとか予算内でやり繰りしたり、工夫したりして制作しています。


『ボクの自学ノート』©NHK
【佐々木】それでも、テレビのほうが自主制作のようなドキュメンタリー映画よりも予算はあると思います。一方で、自主制作のドキュメンタリー映画は予算はないけど「期間」はある。放送日など締め切りが決まっているわけではないので、納得いくまで作れる。だけど、いつ完成するか見通しが立たないので、ずるずるとゴールが見えないままずっとロケを続けることもある。そうすると、編集期間も長くなって、経費もかさみ、完成しないと予算の回収もできない。それだと生活もままならないので、これは万人が目指すべきドキュメンタリー制作のスタイルではないですよね。だから、テレビとか映画とかの区別なく、この本に書かれているドキュメンタリーの方法論は現実的で持続可能な制作スタイルだとと受け止めたんです。
──圡方さんは『さよならテレビ』で制作期間を1年7か月取れたとのことですが、このあたりはいかがでしょうか。
【圡方】会社では「この辺でオンエアーだよ」っていうのは決まってるので、そこに合わせて作っていくという感じですね。確かに、特殊な環境、恵まれた環境ではあったとは思います。ただ、その分逆に編集でぐちゃぐちゃになってしまう。羅針盤がないと、おんなじ素材使ってもまったく違う出来になる。何を捨てて何を取るか。どんな物語でも作れてしまうので、そこはしっかり考えていかないと怖いなと思います。
僕がこの本で一番参考になったのはやっぱり構成の部分なんですね。主人公をずっと木の上まで追いかけて行って落とすんだという例えが出てきますが、ああやって一幕、二幕、三幕を作るというのはほんとにまったく知らなかったので、目からウロコでしたし、それに沿って『さよならテレビ』も作ってます。
伝統芸能や武術の世界には型みたいなものがあるじゃないですか。型を知って、それを崩すのは応用としてあると思うんだけど、崩すにしてもやっぱり型はちゃんと知っておくに越したことはない。知ってて無視するのと、知らずにまったく自由に作っていくのは全然違うなというのは思います。僕も佐々木さんもこの本を読んでるけど、まったくこの型の通り全部やってるかと言ったらもちろんそうではなくて、そこに自分のオリジナリティを出しています。ドラマもドキュメンタリーも、何か物語を紡いでいくっていうことでは一緒。ドラマの世界では当たり前なんだけど、それがドキュメンタリーの人たちはジャンルが違うっていうことだけでまったく知らないっていうのは逆に不思議なことかもしれないです。
【佐々木】もし、ドキュメンタリー作品が職人の世界のように神秘的なワザで作られるものだと言うなら、プロの技術論としてはひどい話ですね。この業界に入って何を学べばよいのかという指針がない。アカデミー賞の「アカデミー」って、「学会」という意味ですよね。要するに、映画をどういう技術を使って作っているのか、みんなで学び合うものだと捉えているんです。だから、ハリウッドを目指す人は脚本術を普通に勉強するんですよね。先ほどから話に出ている「三幕構成」も、僕の解釈では「手法」ではなくて「現象」なんです。いい作品、面白い作品というのは、なぜか「三幕構成」の構造に収斂していくので。
【圡方】なるほど、結果的に三幕になった。そういう意味での「現象」と。
【佐々木】大いなる自然の法則のような。熟練した人は、意識的にも無意識的にも、その法則に則った構成を実践している。自分の場合は、編集はある程度、抜粋を終えたら、冒頭からかなりしっかりと編集していくやり方なんです。放送の時と同じような完成度で作っていって、「今、何分経過してますか?」と編集マンに聞いて、「これぐらいが第一幕の終わりだから、流れやテンポはいい線いってる」とか、「ミッドポイント(中間点)にどんなシーンがきてるかな?」と思って経過時間を確認したら、「ちょうどこのシーンがきているならドンピシャだ!」とか確認しながら編集を進めています。最後、第三幕がどうもハマっていないからまた構成を考え直したり。重要なのは、そうやって最後に一つの作品になったものを見た時、物語の芯がしっかりしていて、第一幕の問題提起に観客が引き込まれて、リズムもテンポもいい、非常に良質な映像作品になっているという事実です。
世界のドキュメンタリストへのインタビューがこの本の巻末に載っていますが、そこでほぼ全員が三幕構成について言及しているんですよね。あらゆる作り手が構成についてのしっかりとした理論を持っている。
この本をすごく気に入って、テレビ業界人の勉強会などで紹介していたら、「佐々木さんって“構成オタク”なんですね」って言われることあるんですよ(笑)。でも、「え? ちょっと待って」と。そもそも「構成」って基本中の基本だし、「まさか、その視点も無く、ドキュメンタリーを作ろうとしているの?」って思います。だから、圡方さんがおっしゃるとおり、「構成」について日本のドキュメンタリー界隈でちゃんと議論されていないとしたら、ちょっと頭を抱えてしまいますね。
【圡方】なんか恥ずべきことだみたいな風潮はありますね。型という言い方は正しいか分からないけど、何か指針があるっていうこと自体がドキュメンタリーというジャンルにおいては恥ずかしいと考えられているのかもしれないです。思い込みとして。
佐々木さんがおっしゃるところの「現象」というのはすごく腑に落ちます。だからたぶんやってることはきっと一緒なんでしょうね。技術を盗んできた昔の人たちからすれば、そういうことが明文化されちゃうことに対しての抵抗というか、それは肌感覚で学ぶもんだと考えているのだと思います。でもみんながそんなふうに肌感覚で先輩から職人のように教われるかって言ったらそうでもない。そういう意味では本があるっていうのはいいことですよね。
【佐々木】世界のドキュメンタリー作家が考えて、実践していることを学ぶのは至極、当然のことですよね。いろんな作家によって考え方は違いますが、方法論でここまで重なる部分があるという事実を無視するなんて、ナンセンスですよ。アレックス・ギブニー監督(『エンロン 巨大企業はいかにして崩壊したのか?』(2005年)、『「闇」へ』(2007年)他)が対談の最後に、「ドキュメンタリストは“形式”について聞かれない」と話しているんです。つまり、作り方や技術論について問われない、と。通常は、取材対象者やテーマの話ばかりになる、というんですね。例えば、圡方さんの作品で言うと「『ホームレス理事長』のあの理事長がスゴイよね」という話に終始して、あの被写体をどう撮影し、どう描いたかという話にならないということです。
『エンロン 巨大企業はいかにして崩壊したのか?』予告編
【圡方】作り手としては、構成ということを意識させず、上手に楽しんでくれたなっていう喜びでもあるんですけど、残念なことに同業者からもそうですからね。『人生フルーツ』(2016年放送/2017年劇場公開)っていうドキュメンタリーができた時に、監督の伏原(東海テレビ)が嘆いていました。社内からは「いいお爺ちゃんとお婆ちゃん見つけましたね」って言われたんだそうで。それぐらい取材対象ありきで、それを見つけたら終わりと思われていると。だけど実はそうじゃないよっていうことが、同業者ですらわかってないのはちょっと悲しいかもしれないです。
【佐々木】すごく分かります。「what」(何を)というテーマについてばっかり語られるんですよね。せめて同じ作り手なら、「how」(どうやって、どのように)について語られるべきだし、もうそういう時代に入っていると思うんですけどね。あらゆる人がスマホで映像を撮れるし、編集も簡単にできる時代ですからね。それなのに、いまだに「映っていた取材相手が面白いね」と、暗に「それで成立した作品だよね」と捉えられてしまう。「いやいや、“how”でしょ?」って。「すばらしい構成だね」とか、「インタビューの聞き方が巧みだね」なんて言われない。『さよならテレビ』って、同業者のプロが見て、プロが大騒ぎした作品なのに、結局「what」の話題ばかりでしたよね。テレビ局の内部を暴いた、暴いてないとか、そんな話ばっかりで、この作品がどう作られたかについて考えが及ばないプロというのは、あんまりじゃないかと思いました。
「作り手の存在」というのが透けて見えるのが当たり前の時代に入っているのに、なぜ、そこには注目しないのか、疑問ですし、そろそろそういう方向に観客の意識も向かったほうがいいと個人的には思っています。もはや、それで作品が楽しめなくなって現実に戻される、なんて感覚ははないんじゃないですかね。
「楽しいドキュメンタリー」
──「how」の重要性にもっと多くの人が気づけば、ドキュメンタリーの世界というのはもっと広がると考えてもよいのでしょうか。
【圡方】「how」を知ることで醒めてしまうことはないですよね。なのでこれからすごく可能性があるジャンルだと思いますよ。エンターテインメントの対極に位置するのがドキュメンタリーで、ストイックに作らなければいけないという考えが薄まっていけば、ジャンルとしてはすごく可能性があるなとは個人的には思っています。ドキュメンタリーが楽しい作品であっていいと思うし、いいように解釈すれば未開の大地だと。
【佐々木】「ドキュメンタリー」って、ジャンルとして他から妙に浮いてるんですよ。先ほどから話に出ている「三幕構成」は、小説、音楽、映画などあらゆるジャンルに通じる概念なんです。でも、ドキュメンタリーだけそれが語られないなんて、むしろ不自然ですよ。それに、最近の映画って、「BASED ON A TRUE STORY」が多いですよね。かなり脚色されていますが、事実をもとにした娯楽作品が大ヒットする一方で、ドキュメンタリーはというと、観客動員はせいぜいミニシアターを埋めるぐらいのレベルにまで落ちてしまうんです。基本的に、多くの人は何らかの作品を見てワクワクしたいんですよね。仮に、社会的な問題を扱った作品でも。大事なことを伝えるためには、休日の時間を割いてお金を払って見に来てもらえるとか、テレビの前に座って見てもらえるとか、そういう行為につながる作品じゃないといけない。だから、そういう意味でも、作り手はドキュメンタリーで観客を魅了する技術についてもっと学ばないといけないですよね。なぜ、ドキュメンタリーだけがさほど工夫もなく、撮影した素材をそのまんま流せばいい、みたいな話になるのか、不思議です。
すごく誤解されていると思うのが、仮に撮ってきた素材をほぼそのまま見せる作品だからと言って、お金や手間がかかっていないわけではないということ。たとえば、東海テレビのドキュメンタリーは、あまり大っぴらに言えないほど予算がかかっていると思います。他の局が真似できないレベルです。でも、そんなイメージを世間の人は抱いていないですよね。あんなに長い期間、ロケや編集を認めてくれる局なんて、そうそう無いですよ。「撮影期間1年」なんて、普通はありえないですから。だからこそ、「どうやって作ったのか?」がもっと話題になるべきなんです。ドキュメンタリーというジャンルのこれからを考えていく上でも、この本は参考になると思いますよ。
【圡方】僕はこの本を教えてもらってから、他にドキュメンタリーの構成に関する本はないか探したんですけど、ないんですよね。ドラマや映画の脚本に関する本はごまんと出てくるんで、その後は映画の構成の本を読んだくらい。そういう意味ではすごく貴重な本だと思いますよね。
【佐々木】映画とドキュメンタリーの方法論を区別する考えは、自分の中にはほとんどないですね。もちろん、被写体に対する責任という点において違うということは、僕も同意します。けれど、方法論がどれぐらい違うかと言ったら、さほど違いはないと捉えています。『さよならテレビ』で圡方さんがやっていたことも、そうですよね。
【圡方】『さよならテレビ』の半分は、実はテレビって視聴者の見えない所でこういうことをやっているんですよといういわゆる暴露でありながら、もう半分はあらゆるものづくり、ドキュメンタリーも含めて何か表現することって、当然制作者の意図が入り込んでくる。良い悪いは抜きにしてそういうものなんだよということを伝えたかったんですね。別に「こんな悪いことをやってまっせ」というのがテーマではなかったのですが、観た人たちからは結構「やっぱり何か悪いことをやっていたんだね」という感想で括られてしまったところはありましたね。しょうがない部分ではあるかと思いますが。
(後編につづく)
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。