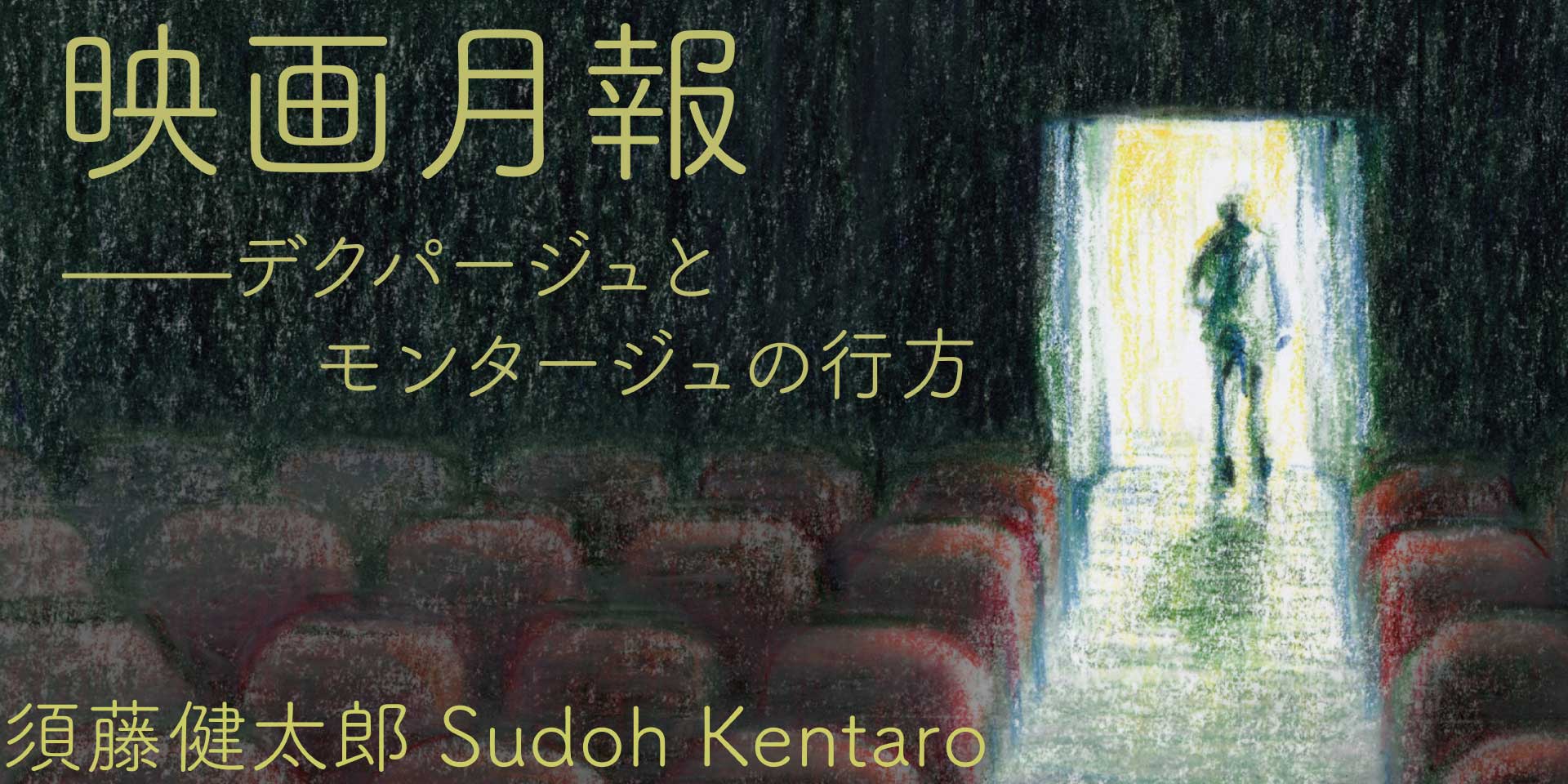映画批評家・須藤健太郎さんによる月一回更新の映画時評。映画という媒体の特性であるとされながら、ときに他の芸術との交点にもなってきた「編集」の問題に着目し、その現在地を探ります。キーワードになるのは、デクパージュ(切り分けること)とモンタージュ(組み立てること)の2つです。
今回はジャン゠リュック・ゴダール監督『軽蔑』と宇和川輝監督『ユリシーズ』。ホメロス『オデュッセイア』を題材とする2つの映画作品についての思索を通じて、映画における「主題」の発見とはいかになされうるかを考えます。
ひとまず『オデュッセイア』の内容をおさらいしておきたいと思って、マンガでわかるホメロスみたいな本を手に取ってはみたものの、似たような絵で似たような展開が続くばかりで驚くほど何も頭に入ってこない。これは無駄なことをしてしまったと、気を取り直して子供向けに『イリアス』と『オデュッセイア』を物語に起こしたものを開いてみると、今度はすんなりと読み進めることができる。言葉を読むのは面倒で絵の方が手っ取り早そうと考えるのはどうも思い込みだったようで、自分にとっては言葉の方がはるかにわかりやすい媒体なのだと気付かされた一件だった。まあ、いつもそうとは限らないだろうけれど。

ジャン゠リュック・ゴダール監督『軽蔑』より、劇中映画『オデュッセイア』の撮影シーン
なぜいまさら『オデュッセイア』? それにはちょっとした理由があった。きっかけはゴダールの『軽蔑』(1963)。フリッツ・ラングが本人役で出演し、劇中で『オデュッセイア』の映画化の話が展開する作品である。東京日仏学院でジャン゠リュック・ゴダールの特集上映があり、そこで『軽蔑』について話すことになったので、自然とホメロスのことも気になったわけだった。
ゴダールの『軽蔑』は原作であるアルベルト・モラヴィアの小説にかなり忠実で、『オデュッセイア』の映画化に関する逸話もモラヴィア経由のそのままである。だが、『オデュッセイア』への関心の向け方はやはり少し異なっており、映画への翻案に際して雇われた脚本家が自分たち夫婦の関係をオデュッセウスとペネロペイアの関係に反映させてしまうというあたりにモラヴィアの関心があったとすると、ゴダールはそうした文学的な仕掛けにはほとんど興味を持っていない。ゴダールはむしろ映画版『オデュッセイア』の中にフリッツ・ラング映画の特徴を見出そうとする。撮影したラッシュ映像を見る試写の場面で、監督は脚本家に向けて説明する——「これは個人が状況と闘う姿です。古代ギリシアの問題の一切がここにあります」。
ラングの発言は、たとえばゴダールのこんな指摘をただちに想起させるわけである——「ラングのシナリオはどれもみな、同じやり方で組み立てられている。つまりどのシナリオにおいても、偶然がある登場人物に、個人主義の殻の外に出て悲劇的ヒーローになり、自分に不意にふりかかった宿命を《ねじふせよう》とせざるをえなくさせるのである[1]」。
これはホメロスに限らず古典の宿命みたいなものだと思うけれど、『オデュッセイア』がヨーロッパで物語の祖型をなしてきたのは、それがすべての元になる形を備えているからではなかったはずだ。むしろそのつど形を変えることができるという可塑性こそが古典たる所以であって、多くの解釈、多くの翻案、多くの二次創作を受け入れることのできないものが古典として残るとは考えられない。『オデュッセイア』が彫刻だとすれば、それはあたかもいつまでも乾いて固まることのない粘土のようなものである。

『ユリシーズ』Ⓒikoi films 2024
宇和川輝の『ユリシーズ』を見たのは、ちょうどこんなことを考えながら『オデュッセイア』を読み直していたころだった。スペインはサン・セバスチャンにあるエリアス・ケレヘタ映画学校の修了制作だという。タイトルからは、ジョイスの『ユリシーズ』を通して、ホメロスともつながりのある作品であろうかと想像させられる。
映画は3つのパートからなる。それぞれ場所も言葉も人物も異なっていて、各パートにどんな連関があるのかは語られないが、『ユリシーズ』のタイトルに誘われるままに、毎回そこに『オデュッセイア』の反響を聞き取るのは難しくない。まず始まるのは、マドリードに暮らすロシア人の母と息子の会話。父親は息子が生まれる前に「宝探し」に出かけたきり、まだ帰ってきていないという。二人はあたかもイタケに残された妻ペネロペイアと息子テレマコスの生まれ変わり。
2つ目のエピソードに切り替わると、舞台はサン・セバスチャンに移っている。バスク語もスペイン語も解さず英語でコミュニケーションをとる日本人の男。彼を優しく迎え入れるバスク人の女。彼女はオデュッセウスに恋をし、7年ものあいだ洞窟に彼を幽閉した仙女カリュプソなのか。あるいは海岸に流れ着いたオデュッセウスを介抱し、国に迎え入れた王女ナウシカアなのか。浜辺で始まる冒頭の場面にせよ、彼を車で送って降ろす終盤のくだりにせよ、いずれも何の変哲もない日常的な情景でありながら、そこに『オデュッセイア』で語られるエピソードを透かし見ることができるようだ。
最終話にして、最も長尺な第3章。照りつける真夏の太陽が、季節と場所が変わったことをひとめでわからせる。ここは岡山県の真庭市。男は、亡くなった祖父を迎えて供養するために、お盆休みに祖母の家に帰省した。この男を監督本人が演じている。宇和川輝は東京の大学を卒業した後、まずマドリードに留学し、次にサン・セバスチャンへと移動して、2つの映画学校を渡り歩いたという。故郷への帰還は、長い放浪の末にイタケに帰り着くオデュッセウスの物語の変奏だろうか。それとも、ここには父の帰還を待ちわびるテレマコスの末裔が現れているのだろうか。

『ユリシーズ』Ⓒikoi films 2024
しかし、と私はここまで考えてきて、一度立ち止まってみた。『オデュッセイア』がそのつど形を変えて何にでも化身することができるなら、古代ギリシアの叙事詩との照応はどこにでも見出せることになる。つまり、宇和川の『ユリシーズ』に古典の面影を探るのはほとんど意味をなさない振る舞いということだ。実際、監督によるプロダクション・ノート「『ユリシーズ』を今振り返る」(劇場用パンフレットに掲載)を読むと、この作品が成長していくなかでは『オデュッセイア』からの離陸こそが核心になったことがよくわかる。3つ目の真庭のエピソードが先立つ2つの部分と性質を異にするのはその点に関わっている。
マドリードとサン・セバスチャンでの試行錯誤を経て、真庭で発見されるのはありていにいえば「主題」である。亡き夫の初盆を準備する祖母の姿を記録した短篇『ある夏の日記』(2022)を翌年にセルフリメイクしたのがこの第3話ということだが、大きな違いは今度は祖母と一緒に監督本人がカメラの被写体になることだ。主題というのは、カメラの後ろから前へと移動することの必然を指す。
主題の発見は、端的にデクパージュの変化に反映されている。1話目のマドリードは切り返しの脱構築から始まっていた。テーブルを挟んだ会話という状況をエスタブリッシング・ショットと2人それぞれのクロースアップで構成するそのデクパージュこそオーソドックスな切り返しに準じるものだが、ショットの持続を引き延ばし、リズムを緩慢にさせることでその用法と効果はまったく異なるものになっている。
この映画では以降切り返しは採用されない。と、思っていると、真庭パートにいたって様子が変わる。カットが切り替わるたびに、カメラの視点が問題にされる。たとえば家族で手巻き寿司を食べる食卓の場面。カメラは祖母と宇和川の背後に置かれ、部屋の外から離れて眺めるように一家団欒の光景を捉えている。カットが切り替わり、カメラは俯瞰気味に祖母と宇和川を今度は正面側から捉えるようになるが、観客の意識は自然と画面奥へと向かう。さきほどまでカメラがあったとおぼしき場所が映されているからだ。祖父の遺品のノートを整理する宇和川と母のくだりも同様である。カメラは洗濯物を干す祖母のかたわらにいたことが続くショットで明かされる。

『ユリシーズ』Ⓒikoi films 2024
死者を迎え入れるお盆という行事。いつも遠慮がちな位置に置かれる(かと思えば大胆に空間に割り込んでくる)カメラはまさに此岸にいっとき舞い戻った死者の視点を代理するようで、そこにいながらにしていない存在である幽霊を思わせるほどだ。いや、不在というかたちで存在するもの、実体なくそこにあるものといえば、カメラの定義そのものなのかもしれないのだが。
何を撮ればいいのか。どうすれば映画が立ち上がるのか。作品を成り立たせる要件は何か。主題はそう簡単に見つかるものではない。宇和川輝は自らを一つの視点として作中に文字通り導入し、また幽霊の存在に手助けされながら、カメラの視点をそこで問題にする。なぜなら、それが長い探究を通してふたたび見出された主題だからである。
ここで再度『軽蔑』に戻る。フリッツ・ラングはこんなことを言っていた。映画には「明確な視点(a definite point of view)」が必要なのだ、と。なお、通訳はそれを間髪入れずに「批判的理性(une raison critique)」と訳すことになる。
註
[1]ジャン゠リュック・ゴダール「『地獄への逆襲』——フリッツ・ラング」(1956年)、『ゴダール全評論・全発言Ⅰ 1950–1967』、奥村昭夫訳、筑摩書房、1998年、p. 157。
『ユリシーズ』
2024|日本・スペイン合作|日本語、スペイン語、バスク語、ロシア語、英語|73分|
監督・編集:宇和川輝
制作:宇和川輝, 関野佳介
撮影:宇和川輝, エイヴリー・ドゥンカン, 関野佳介
録⾳:ニコラス・アウジェー, 吉川諒
整⾳:⻩永昌
出演:アレフティーナ・ティクホノーヴァ、ディミトリ・ティクホノーヴ、エナイツ・スライカ、⽯井泉、原和⼦、宇和川輝
配給:新⾕和輝, ⼊江渚⽉
製作・配給:ikoi films
宣伝協⼒:プンクテ
宣伝ビジュアル:ラウラ・イバニェス
宣伝デザイン:⼆宮⼤輔
製作協⼒:Elías Querejeta Zine Eskola
企画助成:Ikusmira Berriak
Ⓒikoi films 2024
2024年マルセイユ国際映画祭 ファーストフィルム・コンペティション
2024年サン・セバスチャン国際映画祭 サバルテギ・タバカレラ・コンペティション
2024年東京フィルメックス メイド・イン・ジャパン部⾨
2025年全州国際映画祭 インターナショナル・コンペティション
2025年ニューガーデン映画祭 パースペクティブ・ナウ部⾨ オープニング作品
公式ホームページ:https://ulyssesfilm.studio.site/
公式X:https://x.com/ikoifilms
公式Instagram:https://www.instagram.com/ikoifilms/
7月19日(土)〜ポレポレ東中野、8月23日(土)〜シネ・ヌーヴォほか全国順次公開。
バナーイラスト:大本有希子