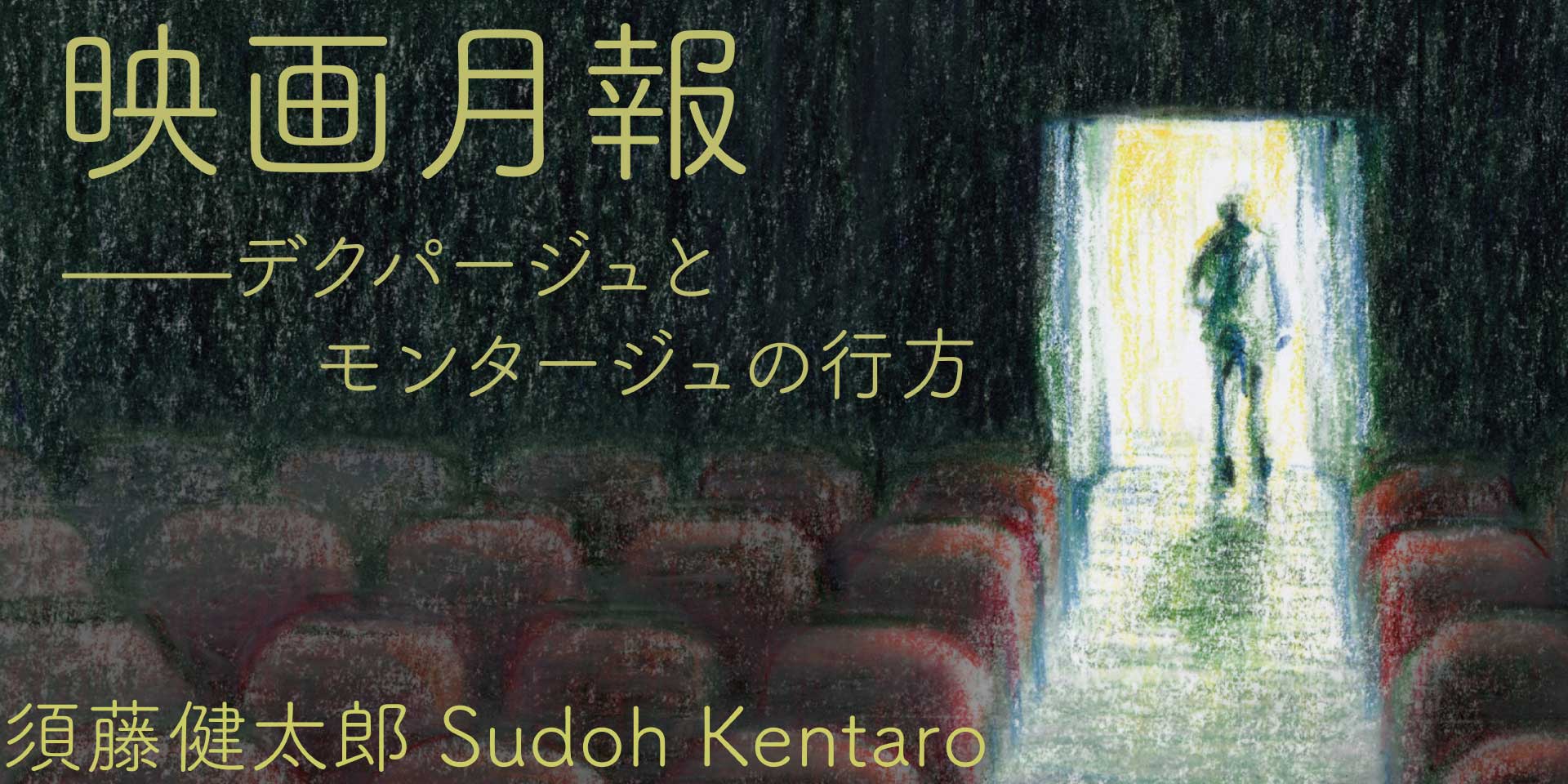映画批評家・須藤健太郎さんによる月一回更新の映画時評。映画という媒体の特性であるとされながら、ときに他の芸術との交点にもなってきた「編集」の問題に着目し、その現在地を探ります。キーワードになるのは、デクパージュ(切り分けること)とモンタージュ(組み立てること)の2つです。
今回はロバート・ゼメキス監督最新作『HERE 時を越えて』。ただひとつのアングルを通じ人類史以前から現代までを語るグラフィックノベルを原作にした本作。そこでのゼメキスの試みについて、5つの問いから向かい合います。
1. これは感動のラストなのか。それとも、おぞましいホラーの幕開けなのか。
それまで見てきたすべての場面が一つの場面に集約し、そこにすべての時間が積み重なっていく。その力業に思わず心を動かされながら、いや、巻き込まれてはいけないと、同時に警戒心を抱く自分もいた。妻はこの家が嫌だとあんなにも繰り返していたではないか。夫は妻の言い分を理解せず、父から受け継いだこの家にこだわった。その結果、妻はついには家を出て行ったではないか。時は流れ、売り家となりもぬけの殻となったかつての住処に、夫は妻を招く。いまや認知症が進行して記憶をなくした妻に、夫は優しくささやきかける。僕たちは仲良く暮らしたね。ここには素晴らしい思い出がたくさんあったね、と。あたかも彼女の記憶を塗り替えるようにして。
この家は、先住民から奪った土地に立てられた。そんな場所で繰り返される「アメリカ」の物語。偽りのホーム・スイート・ホームを仮構することでしか幸せを演出できない、哀れな男たち?

©2024 Miramax Distribution Services, LLC. All Rights Reserved.
2. 本作はゼメキスの新たな一歩なのか。それとも、これまでどおりの反復なのか。
トム・ハンクスとロビン・ライトは10代から70代にいたる、異なる年齢をすべて自分一人で演じきっているという。VFX(視覚効果)を巧みに使うことによって、二人を自在に若返らせたり年老いらせたりできるようになった。それは膨大な量のデータをAIに学習させて、さまざまな年齢の顔貌を出力させるという意味では最新技術の成果なのだろう。だが、ゼメキスは2000年代初頭に誰より熱心にモーション・キャプチャー取り組み、CGアニメーションの連作を手がけていた。本作のVFXはその延長線上にあるはずだ。『ポーラー・エクスプレス』(2004)では、トム・ハンクスは一人6役の異なるキャラクターを演じ、少年さえもがトム・ハンクスの動きのデータをもとに作られていた。『Disney’sクリスマス・キャロル』(2009)のジム・キャリーは一人7役に挑んだが、とりわけ同じ人物の少年時代、10代、20代、そして年老いた現在の姿をすべて自分一人で演じ分けていた。
そもそも『フォレスト・ガンプ/一期一会』(1994)のスタッフとキャストの再結集と謳われる『HERE 時を越えて』。ここにゼメキス映画の諸要素がパッチワークされていてもおかしくはない。同じ場所に留まりながら異なる時間を移動する。それは「バック・トゥ・ザ・フューチャー」3部作(1985–90)ですでに挑戦済みのこと。もっと細かなこともある。たとえば劇中、テレビに『エド・サリヴァン・ショー』が映り、ビートルズの演奏が流れるくだり。誰もがゼメキスの長篇デビュー作『抱きしめたい』(1978)を想起するだろう。ビートルズが初めてアメリカ合衆国に降り立ち、『エド・サリヴァン・ショー』に初出演した1964年の出来事を描いた作品である。
3. ゼメキスは革新的な表現を狙ったのか。それとも、伝統への回帰を図ったのか。
原作グラフィック・ノベルの作者リチャード・マグワイヤは、着想源の一つはコンピュータ・ディスプレイ上のマルチウィンドウにあると明かしている[1]。とすると、ゼメキスの『HERE』にもたとえば『search/サーチ』(アニーシュ・チャガンティ、2018)に通じるものがあるかといえば、そんなことはない。
もとよりマルチウィンドウが映画に新しい意匠をもたらさないことをやぶれかぶれに告げたのが『saerch/サーチ』だった。終盤でPCモニターをニュース番組の画面に明け渡し、遊びを成り立たせていた制約にしてルールをかなぐり捨ててしまうからだ。『HERE』はあたかも『search/サーチ』と同じ轍を踏むことだけはすまいとでもいうかのように、テレビにはラジオと同様の時代背景を説明するという機能しか与えない。また、カメラや鏡を導入して別のアングルから見られた光景が画面内に入れられはするが、簡易スクリーンの上に映写されるホームムーヴィーにはすでに観客が見たものしか映らない。鏡によってカメラの背後の空間が映されるといっても、そこにいるのはよく見知った二人でしかない。いずれも物語の展開には奉仕しないものがあえて選ばれている。
マルチウィンドウがコンピュータ画面特有のものだとすれば、リチャード・フライシャーが『絞殺魔』(1968)で自覚的に示したように、1960〜70年代にスプリット・スクリーンが流行したのはやはりテレビの一般化と軌を一にしていた(ロイス・ウェバーとフィリップス・スモーリーが『サスペンス』(1913)で早くも分割画面を使用したのは知られるとおりだが、それは実際には同時代に隆盛を極めたクロス・カッティングの代替物と考えるべきである)。多くのモニターが居並ぶ管制室の光景こそがその原像であり、マルチカメラ撮影によって一つの出来事が同時に複数の視点から捉えられ、生放送によって異なる空間の同時性が顕在化した。『HERE』では画面上に複数の画面が並列されるといっても、単一の視点が維持される以上、それはスプリット・スクリーンの美学とは似て非なるものである。

©2024 Miramax Distribution Services, LLC. All Rights Reserved.
4. 『HERE』は時間の旅なのか。それとも、空間の旅なのか。
この作品は編集という点からみれば、きわめて伝統的で古風な意匠しか用いない。テレビ以前の映画に範を取ったものであり、基本となるのは並行モンタージュである。リチャード(トム・ハンクス)とマーガレット(ロビン・ライト)のエピソードを基調にしながら、時代の異なる複数の家族のエピソードが交互に語られていく。
20世紀初頭、この家が建てられ初めに住んだのは飛行機に熱中する夫とその妻。その次は、発明家の夫とピンナップ・ガールの妻が第二次大戦まで住み、戦後に越してきたのがリチャードの両親である。この家の窓からは、向かいに建つ邸宅が見える。ときは18世紀、そこに住むのはベンジャミン・フランクリンの婚外子ウィリアムだ。親子はアメリカの独立をめぐって意見を対立させている。さらにそれ以前に遡ると、イギリス人が入植してくるまで、ここには先住民の暮らしがあった。2024年現在、家はいま売りに出されている。リチャードの退去後はアフリカ系の家族が移り住み、2020年にはここにもコロナウィルスの脅威が襲いかかった。
いくつもの物語が交錯するといっても、それぞれのエピソードはあくまで単線的に進み、各々の時系列が乱されることはないので、けっして複雑な構成の映画ではない。また、エピソード間の移行はいつも滑らかで、誰もが親しむ伝統的な手法ばかりが頼りにされる。
ある時代のエピソードが進むなか、画面の一部が小さく切り抜かれ、そこに別の時代(物語)が現れる。そして、その一部が次に全体を占めることで場面が転換していくのだが、要は、画面内に現れる小さな画面はかつてサイレント映画の時代にアイリスが担っていた役割を引き継いでいるのである。あるいは、次のエピソードが小さな画面の中に先行して現れ、徐々に移行していくような場合には、この分割画面がディゾルブと同じ機能を担うことになる。あるときはモーフィングが使われたりもするが、それもあくまでデジタル時代のディゾルブとしての位置付けである。家の雨漏りとマーガレットの破水、2020年代のコロナ禍と1920年代のスペイン風邪など、モチーフの類似や連関を通して各場面がつながれることもあるが、これもまた映画がずっと得意としてきたものだ。いくつもの画面(時代)が乱立する場面に接すれば、それがモンタージュ・シークエンスに相当するとすぐ気づく。

©2024 Miramax Distribution Services, LLC. All Rights Reserved.
5. ここにはどのような同時代性があるか。
画面内に現れる小さなフレームがアイリスの等価物だとするなら、その画面内画面はときにクロースアップの機能を有していることになる。『HERE』を特徴付けるのは定点観測ではない。ときにはクロースアップ、ときにはミディアムショットといったフレームサイズの異なるいくつものショットを取り出すことができる一つのマスターショットを得ること、それがなにより重要なのである。
なぜなら、高解像度のカメラが開発されて、そのような撮影・編集方法が現実のものとなっているからである。たとえばバルベ・シュロデールの『忘れられない記憶』(2015)がそうだという[2]。この作品は8Kカメラで撮影されているが、撮影時には全体を収めるマスターショットを撮っておき、ポストプロダクションの段階でその一部を切り抜き、必要なクロースアップやツーショットなどを作り出して再構成しているとのことだ。
マルチカメラとズームの導入によって、デクパージュ(カット割り)のプロセスは骨抜きにされた。8Kカメラが1台あれば、カメラを複数台用意する必要もなくなり、どこでも好きな部分にズームして任意のショットを事後的に作り出すことができる。今後、デクパージュの概念はさらなる変容を被らざるをえないのではないか。『HERE』が示唆するのは、そんな現在のことである。
変わり映えのしないこのリビングを描いて飽きないと、リチャードは父親から嗤われる。いや、実際は、マスターショットの中からお望みのショットを次々と作り出すことを彼は若くから始めていたのだ。終盤にいたり、彼の絵が室内に一斉に並べられる。その光景には、リビング全体を捉えたマスターショットからどれだけ多彩なショットを取り出すことができるかが示されている。
註
[1] Cf. 「訳者あとがき」、リチャード・マグワイヤ『ヒア』大久保譲訳、国書刊行会、2016年。
[2] Cf. フランシス・フォード・コッポラ『フランシス・フォード・コッポラ、映画を語る——ライブ・シネマ、そして映画の未来』南波克行訳、フィルムアート社、2018年。
『HERE 時を越えて』
原題:HERE
2024年|アメリカ|英語|104分|ビスタ|カラー|5.1ch|
監督:ロバート・ゼメキス
原作:リチャード・マグワイア
脚本:エリック・ロス、ロバート・ゼメキス
撮影:ドン・バージェス
編集:ジェシー・ゴールドスミス
出演:トム・ハンクス、ロビン・ライト、ポール・ベタニー、ケリー・ライリー、ミシェル・ドッカリー
字幕翻訳:チオキ真理
提供:木下グループ
配給:キノフィルムズ
©2024 Miramax Distribution Services, LLC. All Rights Reserved.
全国公開中
公式サイト:here-movie.jp
公式X:@HERE_movie0404
バナーイラスト:大本有希子