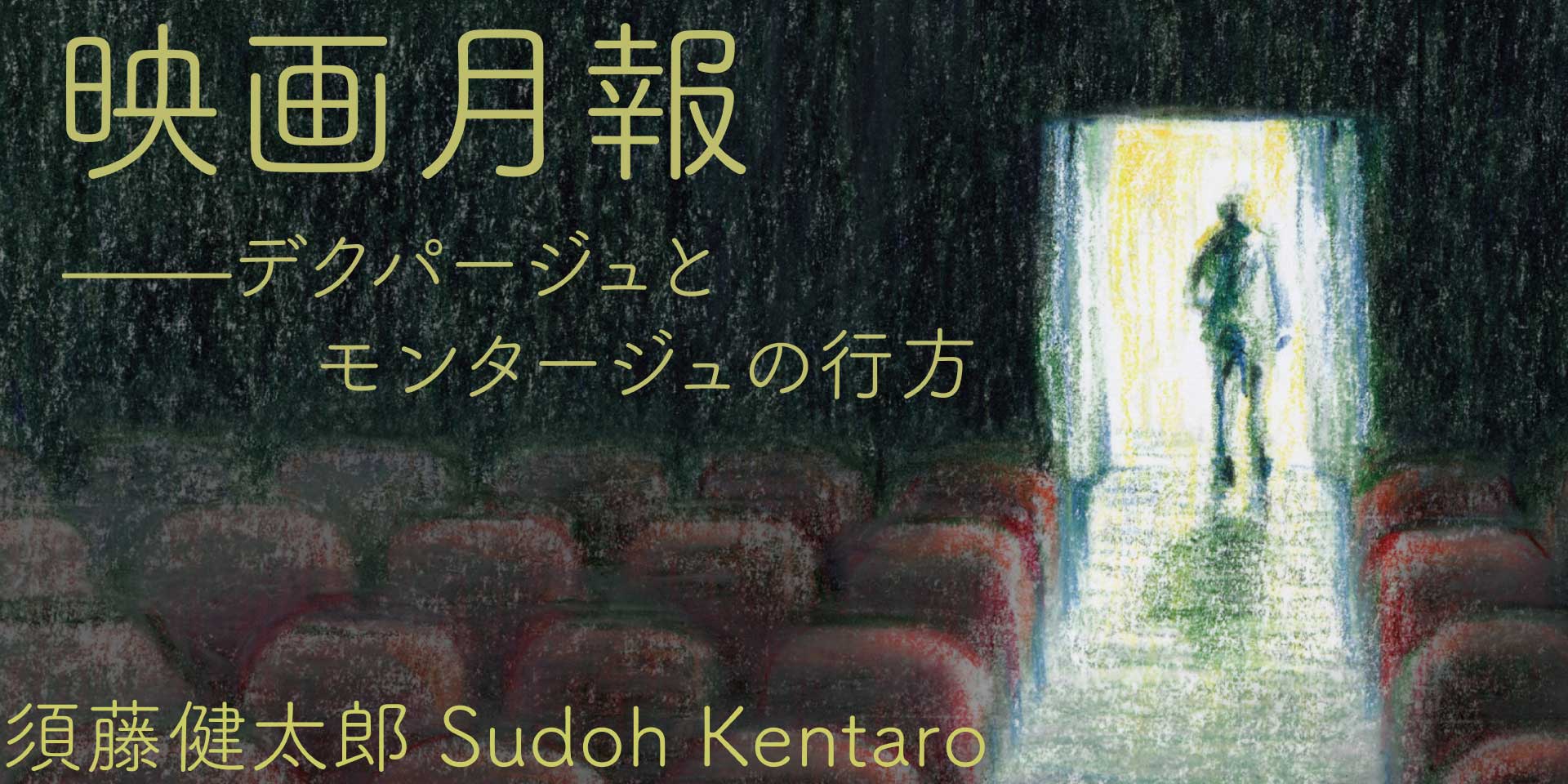映画批評家・須藤健太郎さんによる月一回更新の映画時評。映画という媒体の特性であるとされながら、ときに他の芸術との交点にもなってきた「編集」の問題に着目し、その現在地を探ります。キーワードになるのは、デクパージュ(切り分けること)とモンタージュ(組み立てること)の2つです。
今回は佐向大監督『中山教頭の人生テスト』。佐向監督が『夜を走る』の工場を経て、本作では小学校を舞台に見出した「スクラップ」とは、いったいいかなるものなのでしょうか。
かつてハリウッドが工場に喩えられ、フォーディズムの確立とスタジオ・システムの発展の同時代性がまことしやかに語られもしたように、映画の古典時代は工場とともにあった。もともとは機械の組み立てを意味した「モンタージュ」という語が映画業界で編集を指すようになったのは偶然ではない。一方、リュミエール兄弟は映画史を『工場の出口』(1895)から始めた。映画は工場の中ではなく、その外にあると見抜いていたからだ。「産業の終わりとともに、映画は始まる」。1970年のジャン゠マリー・ストローブの発言をあたかも「先取りによる剽窃」(ウリポ)してみせたかのように。
『夜を走る』(2021)でスクラップ工場を舞台にしたとき、佐向大は映画史をこのような認識のもとに把握していた。そして、そのうえで自らの立ち位置を明確にした。映画的な、あまりに映画的な工場を被写体にするといっても、いまや問題なのは構築すること(モンタージュ)ではない。しかも、ここに出てくる武蔵野金属は解体工事を請け負う会社でもない。工場以後の映画にとって、問題なのは解体すること(デモンタージュ)でもないということである。解体後に残された鉄くずを集めること、佐向はそこに現在の映画の使命を見出そうとした。『ウイークエンド』(1967)に「鉄くず置き場で見つけた映画(un film trouvé à la ferraille)」と副題を付し、すでに映画の解体作業をひと通り終えたという自負を示したゴダールに、彼はかくして連なってみせたのである。

©2025映画『中山教頭の人生テスト』製作委員会
では、映画において、スクラップとは一体何を指すのか。解体の後に残された鉄くずとは何か。かつては作品の形成にとって大事な材料であり要素であったもの。だが、すでに使い古され、用無しとなったもの。たとえば、紋切り型とかクリシェと呼ばれるようなもの。
武蔵野金属がステレオタイプの描写に満ちているのは、つまり理の当然なのである。社長のゴルフ、昼食時の下ネタ、社内不倫、チャラい若者と奥手の中年、上司のパワハラ、行きつけのフィリピンパブ、営業に来た若い女へのナンパ、どれもこれもどこかで聞いたことがあるようなものばかりだ。殺人の顛末も典型的なフェミサイドであり、自己啓発セミナーの様子も衆人の想像力の域を出るものではない。カラオケでは既成曲のかわりにいかにもありそうな曲がオリジナルで作られていて、そのあたりに監督の自覚が顕著に現れている。クリシェとは現実そのものではない。現実から抽出されてはいても、あくまで想像の産物なのである。ちなみにカラオケの場面は、高音を出し終えたタイミングで「きちー」と差し挟む、そこまで含めて「あるある」が徹底される。
振り返ってみると、『教誨師』(2018)の面会室もまたその意味でスクラップ工場だった。大杉漣演じる牧師の佐伯が6人の死刑囚と対話するさまが描かれるなかで、囚人たちはそれぞれがその役を裏切ることのないような演技を披露している。関西弁で陽気なおしゃべりに興じる烏丸せつこにせよ、ストーカー殺人を犯し、いまだに自分の妄想に閉じこもる古館寛二にせよ、気の良いヤクザの光石研にせよ、誰もが自分の役をいかにもその役らしく体現する。また、玉置怜央演じる死刑囚は、知的障害者福祉施設の津久井やまゆり園で入所者19人を殺害した植松聖をモデルに造形されている。自らの行為を正当化する植松の詭弁がなにも特異なものではなく、現在の日本社会から必然的に生じざるをえない常套句であることを示すには、一般に共有されたイメージをあえてなぞるだけの演出が必要だった。
中盤、牧師の佐伯が亡き兄のことを思い出し、その兄が面会室に現れるように、『教誨師』はこの面会室の空間自体を佐伯の内面として設計している。それぞれの囚人との対話は、その実ほとんど自己との対話にすぎない。この映画がクリシェの集積として成り立っているのは、ここに展開するすべてがこうして一人の登場人物の想像力のうちに収められるからだ。

©2025映画『中山教頭の人生テスト』製作委員会
『中山教頭の人生テスト』の小学校もまたスクラップ工場に見立てられている。ここに登場する人物も彼ら彼女らが織りなすエピソードも既視感に満ちているではないか。平凡さが売りの教頭が自転車で通勤する一方、型破りだけど児童からは人気の先生がスポーツカーに乗っているとか、優等生が実はいじめの首謀者だとか、土建屋の息子がやんちゃ気取りとか、シングルマザーは夜職で言葉遣いが荒いとか、その娘が非行に走るとか、はたまた教育委員会の教育長が結局は実権を握っていて、ホモソーシャルな組織構造が保たれるとか、どこを切り取っても錆だらけの残骸が現れる。
だが、佐向は前作『夜を走る』の問題意識を引き継ぐばかりではない。小学校というと、社会の成員が作られるまさに工場のような場所と学校を捉えて、そのあり方を肯定的に論じる主張がいま多くの支持を集めているように見えるからだ。小学校にスクラップを集めるとは、そんな現在のおぞましい趨勢に水を差す振る舞いにちがいない。

©2025映画『中山教頭の人生テスト』製作委員会
正直にいうと、この映画の野心に気付くまでには少し時間がかかった。最初はむしろ、いまどき珍しい丁寧に構築された映画として受け取っていた。たとえば冒頭の朝礼の場面で、中山教頭がメモを取るその手元を捉えたミドルショットから校庭全体を映すロングショットに切り替わるくだり。メモを取る中山教頭の姿がロングショットの画面奥で変わらず捉えられており、フレームサイズを移行するにも身振りの一致に配慮せずにはいられない細やかさが印象づけられる。しかも、このメモの仕草を通じて、続く教員会議の場面へと転換してみせるのだから、なおさらである。色調を統一して時間帯と空間の別を明示するような照明の設計にせよ、ショットの積み重ねによる呼吸の作り方にせよ、いわゆる古典的な画面作りと編集に基づく作品と早とちりしたわけだった。
そう単純な映画でないと気付くのは、中盤にいたり、椎名先生が茉莉の証言でクラスの実情を知るくだりに接したときだった。というのは、おそらくほとんどの観客が愛里沙の優等生ぶりが先生向けの演技でしかないことにこの段階ですでに思い至っているはずで、フラッシュバックはいかにも冗長に映るからである。
不要なことがあえてなされている。一度見たショットがもう一度映され、そこに別の意味合いが付与される。ところが、二度目のショットが驚きを生まないように、ショットの連鎖が組み立てられるということである。この真相発覚のくだりにかぎらず、多くのショットが執拗なほど繰り返される。ここではショットをリサイクルすることそれ自体が問題であり、その効果はあらかじめ骨抜きにされている。スクラップ工場は鉄くずを集めては加工し、リサイクル業者にそれを売り渡すだけなのだから。
冒頭の朝礼は、後半には説明会の場面として繰り返される。たまらず立ち上がる椎名先生がインサートされると、それを目で追う中山教頭を挟んでロングショットに切り替わり、体育館から出て行く彼女の姿が画面奥に捉えられる。だが、このとき、観客はすでにこの流れがつなぎへの意識からなされたものではないことを知っている。つなぎへの配慮もまた、いまや鉄くずさながらの過去の遺物でしかない。監督の冷徹な現状認識に目を閉ざすなら、作品の核を見失うことになる。

©2025映画『中山教頭の人生テスト』製作委員会
「先生や大人がこうしなさいって言うことは全部まちがっている」。中山教頭の教えは彼自身が先生であり大人であるかぎり、有名な「嘘つきのパラドクス」と同じように自己言及のパラドクスを体現するものだ。スクラップ工場と化した小学校では、教訓もまたその機能をすでに失っている。
『中山教頭の人生テスト』
2025|125分|カラー・ビスタ・5.1ch|日本
監督・脚本:佐向大
企画・原案・プロデューサー:小池和洋
撮影:沖村志宏
編集:脇本一美
出演:渋川清彦、高野志穂、希咲うみ、渡部秀
高橋努、風間杜夫、石田えり
制作プロダクション:STUDIO NAYURA
製作:「中山教頭の人生テスト」製作委員会
配給:ライツキューブ
©2025映画『中山教頭の人生テスト』製作委員会
公式ホームページ:https://nakayama-kyoto.com/
公式X:https://x.com/nakayama_kyoto
新宿武蔵野館、恵比寿ガーデンシネマほか全国順次公開中
バナーイラスト:大本有希子