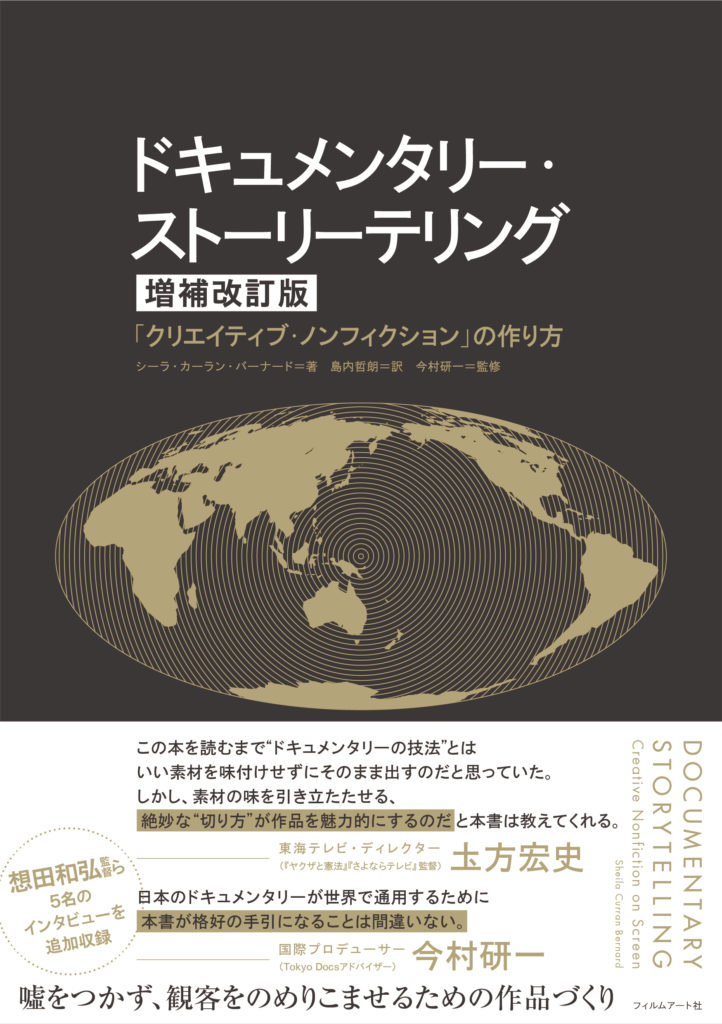2020年10月24日発売『ドキュメンタリー・ストーリーテリング[増補改訂版] 「クリエイティブ・ノンフィクション」の作り方』。ドキュメンタリーやノンフィクションの作品作りに必要な知識が詰まった1冊です。今回の増補改訂版の刊行にあたり、2014年刊行の旧版を愛用されている圡方宏史さん (東海テレビ・ディレクター、『ヤクザと憲法』『さよならテレビ』ほか、以下 圡方)、佐々木健一さん(NHKエデュケーショナル・ディレクター『ブレイブ 勇敢なる者』シリーズ、『ボクの自学ノート』ほか、以下 佐々木)のお二方に、本書の魅力や、現場から見た日本のドキュメンタリー制作の現状を語っていただきました。
「やらせか否か」が未だにテーマになり得るのか
──『さよならテレビ』のそういった意図は、現代ではさもすると「やらせ」としてバッシングの対象にあってしまうものなのかなとも思っていました。やはり制作をされるうえでそのあたりはとくに意識されていることなのでしょうか。
【佐々木】ドキュメンタリーに関しては、いつもその話題が出てきますよね。最近も『テラスハウス』や『ザ・ノンフィクション』でのやらせ告発(ともに2020年)がありましたが、「ないものをあるとする」のは、やっぱり駄目だと思うんです。ただ、あったものをどう再現するかということは、普通の手法としていろんな作家がやっていますよね。
僕らは撮影に行く前に、必ず準備をする。ちゃんと場所や動線を確認して、取材対象者に「こういう話を聞きますよ」という説明もして、それから「さあ、撮りますよ」と撮影するんです。もし、そうした過程を踏まなければ、全て出会い頭にいきなり撮影する格好になりますから、失礼極まりない。お宅を訪問する時も、コンコンとノックして「こんにちは」と入っていく。いきなり訪問と同時に撮影を始めたら、撮られる方はビックリしてカメラ目線になるし、「なんで、勝手に撮っているの?」という反応になる。だから、あらゆる現場で撮影前の準備は普通に行われていて、その準備の過程で僕らは状況設定(演出)をするわけです。こういう状況設定をしたら、こんなことが起こるんじゃないか、この人とこの人が会ったらこんな話が展開されるかもしれない、とか。これを自分は「演出」と捉えているんですけど、極端な見方をすれば「それって、会う必要のない二人を作り手の都合で会わせているんだから、やらせじゃないの?」と言う人もいるかもしれないですよね。
【圡方】言われかねないですね。
【佐々木】大原則として「ないものをあるとする」のはNGだとして、ドキュメンタリーにおける演出=状況設定と捉えると、ありとあらゆる撮影現場がグレーゾーンに片足を突っ込んでいるとも言えます。
例えば、拙作『ボクの自学ノート』でいうと、主人公の梅田明日佳くんは基本的に楽しい思い出しかノートには書いていないんです。家族内でも、お母さんと息子の間で嫌な話はしない。だけど、自分はディレクターとして、彼の自学ノートを手にした様々な人に話を聞いた上で、僕が思う明日佳くんにとっての“核心部分”をドキュメンタリー番組のインタビューで初めて聞き出すわけです。すると、自分の深層心理のような、これまで誰にも言っていない秘めた気持ちを彼が言葉にして僕に向かって発するようになるんです。それってある意味、それまで世の中に存在していなかったものをインタビューという状況設定によって引き出してしまったわけですよね。つまり、作り手である自分が介入することで、「ない」から「ある」に変わった。でも、これがやらせかというと、やらせではないですよね。


『ボクの自学ノート』©NHK
【圡方】『さよならテレビ』でも同じようなことがありました。澤村さんという中年の記者が共謀罪を追っかけていて、対象の人が裁判で無罪になるというときに、講演会で二人を引き合わせる場をセッティングしたんです。澤村さんに声を掛けて、ピンマイクを仕込んで、取材対象に「澤村さんが来ていますよ」みたいな感じで間を取り持つところを使っています。澤村さんはもともと新聞社で働いていたということもあって、あれに対しては抵抗がすごくあって「テレビの闇」とおっしゃるわけですが、そこで会ったときに彼らがする会話は紛れもない本物だし、彼らが会わなかったら出てこなかった現象を僕が作り出しているというのも間違いないです。彼らのしゃべりにはうそはなくて、思ったことをそのまましゃべっている。台詞を書いているわけではない。
【佐々木】要するに、そうした状況設定(演出)まで否定してしまうと、すべて起きている現象を追っかけ回すしかなくなるんです。今、圡方さんは事前に「ピンマイクを仕込んだ」と言いましたよね? ピンマイクを仕込まないとプロとして失格なんですよ、僕らの常識から言うと。音声が拾えないですから。それも、事前にこれから起こることを想定した準備なんです。この「準備」という行為が、僕はすごく重要だと捉えていて、「構成」もまさに準備なんです。この本でジェームズ・マーシュは「60ページの構成台本を事前に書いた」と言っていますが、それを読んで「そうか、台本通りに撮ってくるものなのか」と受け取られかねないんですけど、決してそうではないんです。
なんとなく、とりあえず現場に行って結局「何も面白いことが起きませんでした」となった時、編集室で無理やり撮影素材から物語を作るようになっちゃうんですよ。これなんて、まさに「ないものをある」にする「やらせ」的な行為だと思います。
そうした問題意識もあって最近、僕はむしろ昔のフィルム時代のドキュメンタリストの作り方にすごく興味があるんです。例えば、大島渚の『忘れられた皇軍』(1963年)も、わずか数分しか撮影できない時代の名作ドキュメンタリーですが、あの頃ってカメラを回せる物理的な時間がものすごく限られているわけですよね。だから、実はカメラを回す前に散々、いろんな話を取材相手としゃべっているんですよ。それで準備が整って、現場の熱量が高まって、「さあ!」という瞬間にようやくカメラを回しているんです。それで、すごいシーンを撮っている。たった数分しか勝負できない世界で。原一男の『さようならCP』(1972年)もそうですよね。「ここぞ」というところでしかカメラを回せない条件下で、先人たちはすごいシーンを撮っていた。
今はデジタル技術が発展して、いくらでもカメラを回せるようになりましたけど、ずっと撮影されていると取材相手も嫌ですよね。さらに、ちょっとしたミスやトラブルがあったシーンだけ使われて、「こういう人です」と描かれるのも最悪ですよね。だから、自分の場合は、ワンショット・インタビューにこだわって、お互い合意の上での真剣勝負から言葉を引き出す制作スタイルへ寄っていったんです。ドキュメンタリー界隈の業界用語で「仕掛ける」という言葉があるんですけど、あまり好きじゃないんです。「何か面白いこと起これ!」と、トラブルを期待する方向へ持っていくような関わり方が、すごく嫌で。そういう点でも、この本には制作者の取り組み方や心得についてもちゃんとしたことが書かれていると思います。
【圡方】この本にはプロとしてどこまでがよくて、どこからが駄目なのかという線引きが書かれていましたよね。因果関係が変わっちゃう時系列のいじり方っていうのはあかんよ、というのを、マイケル・ムーア監督の『ロジャー&ミー』(1989年)を基にして書かれていました。ドキュメンタリーの制作者の数がそもそも少ないものだから、不文律みたいな感じになっているところで、それはよくてそれは駄目なんだ、というのが確認できるのが大きいかもしれないですよね。
【佐々木】それにしても、ドキュメンタリーって何十年経ってもなぜ、必ず「やらせ」とかの話になるんでしょうね。『さよならテレビ』のラストシーンでも、まさにそうしたテーマを扱っていました。圡方さんは、森達也の『ドキュメンタリーは嘘をつく』(草思社、2005年刊)が好きだと言っていたし、最初にラストのカットバックシーンを見た時は、北野武監督『あの夏、いちばん静かな海』(1991年)みたいに感じて、そういう編集自体はすばらしいと思ったんですけど、あのラストシーンで描いているような“虚実”みたいなことが未だにテーマとして成り立つのかな、という疑問が僕にはあるんです。ドキュメンタリーというものを語る時に、まだその議論が続くのかぁ、という。古くは、今村昌平の『人間蒸発』(1967年)で、もうやってますしね。
【圡方】最後にバターンとなるやつですね。
【佐々木】要するに、ドキュメンタリーは「真実」か「噓」かみたいなテーマ。その境界で彷徨っていることも含めて、未だにそうした議論が続くのか、と。このことについてはよく「プロレス」を例えに話をするんですが、僕らはUWF世代なので「UWF幻想」を通じて思春期から青年期にかけて「信じていたものに裏切られる」という貴重な経験を積ませてもらった。プロレスに対して格闘技路線のUWFが出てきて一時期、熱狂したわけですが、実はUWFもちゃんと彼らのスタイルのプロレスを実践していたと大人になって知ったんですね。で、その過渡期において総合格闘技という真剣勝負も目の当たりにしてきた。
そういう通過儀礼を経て、今ではもうプロレスと総合格闘技の違いが分かっていないファンって、いないんじゃないかと思います。ちゃんと分かった上でそれぞれ楽しんでいる。プロレスも輝いているし、総合格闘技も輝いている。そういうリテラシーの時代を今、僕らは生きているんです。だから、ドキュメンタリーやノンフィクションに対する見方も、先ほど話した「whatではなく、how」という見方で、「この作り手・書き手はものすごく巧みな描き方で事実を伝えている」といった見方をされてもいいはずなんですよ。プロレスでいうなら「プロレスがうまい」という表現のような。
そして、実際にすれすれのグレーゾーンも存在するわけですよね。プロレスだって死んでしまう選手もいるし、選手同士のいざこざでリアル・ファイトになることもある。それってフィクションとノンフィクション、ドキュメンタリーと劇映画の関係に似ている感じがするんです。プロレス・格闘技ファンはすでに今、先ほど言ったリテラシーの上に立っているんです。どちらかを否定するようなやつは「お前は一体、いつの時代にいるんだよ」とバカにされるんですね。そうした視点に立つと、「ドキュメンタリーって、未だにこんなことを言わなきゃいけないの?」という感じが僕はしちゃうんですよ。
【圡方】なるほど、確かに。報道のように現実をそのまま映していると思われているものは実はそうではなくて、そこには制作者の意図が入ります、というのは、多分一般的にはまだ浸透していないかもしれないですね。そういうリテラシーが必要なんですかね。それを『さよならテレビ』ではああいうラストで提示したわけですが。
【佐々木】作り手次第で、いい撮影素材が揃っていてもひどい駄作になったり、すばらしい名作になったりするのは、作っている側からすると当たり前のことじゃないですか。だけど、ドキュメンタリーを見る観客は、まだそういう感覚を持ててはいない。ほぼ、映っていることや被写体しか見ていない。
【圡方】それはさっき佐々木さんが言ったところの持続可能性とも関わりますよね。リアルファイトばかりずっとやっていたら死んじゃうじゃないですか。でもまさに今はそういう時代で、素人でもリアルファイトですごいものが撮れたら、1回はオッケーなんです。だけど僕らはやっぱりプロだから、それをコンスタントに生業としてやっていかなきゃいけない。本気で痛いし、血のりじゃなくて流血もするんだけど、でも死にはしないし、リングにも立てるぎりぎりのところをいくというのが、これからプロがちゃんと残っていくための1つのポイントになるのかな、とプロレスの話を聞いて思いましたね。
【佐々木】「人の人生を左右するようなテーマを扱うんだから、ドキュメンタリストは毎回、血を流す真剣勝負であるべき!」みたいな感覚が、何となくこのジャンルにはあったんですよ。プロレスや格闘技でいえば、パンクラチオンの時代まで遡る命の削り合いのような。でも、そのスタイルでは持続できないですよね。
この本で『戦場でワルツを』について、ジェームズ・マーシュが「この作品は『全ては主観である』という批評にもなっている」と言っていますよね。客観性や神の視点ではなくて、「ドキュメンタリーは主観である」と言い切っているんです。「客観的なものなどありえない」と。
【圡方】まあないでしょうね。
【佐々木】ないんですよ。「全ては主観である」という事実からは逃れられない。ですから、ある作品はあくまで「作り手が今、世の中や取材対象をこう見て、1つの結論としてこうまとめた」というものなんですよね。
もっと言うと、ドキュメンタリーを撮っていて感じることなんですが、自分と全く境遇が違う相手を取材していても、結局、作り手は自己投影していくものなんですよね。自分が撮影し、素材を選択して構成していく過程で、自分のストーリーを仮託していってしまうんです。意識的にも無意識的にも。
「自分の作品」としてのドキュメンタリー
──近年の佐々木さんの作品は「本筋とは関係ないと思われたインプット」がそれぞれの作品に深く影響しているなと思いました。『Mr.トルネード』(2016年放送)も、気象学者ではない出自だからダウンバーストを発見できたということでしたし、『硬骨エンジニア』(2017年放送)も営業職の経験があったからフラッシュメモリの発想が生まれた。『ボクの自学ノート』(2019年放送)もまさにそういうことですよね。



ブレイブ 勇敢なる者『Mr.トルネード~気象学で世界を救った男~』©NHK
【佐々木】今、言われて初めて気づきましたが、確かにそうですね。それは、自分自身のキャリアがまさにそうなんですよ。ドキュメンタリーが作りたくてこの業界に入ったのに、うちの会社は基本的に教育番組の制作が多いんですね。だから、入社当初は健康番組や料理番組を担当していました。30歳になるぐらいまでずっとそうした番組をやっていたんです。結構、驚かれます(笑)。その間、異動を繰り返して「あ〜、俺、いつになったら『延安の娘』みたいな番組を作れるんだろう」と思って、ちょっと拗ねていた感じも正直、ありました。でも、結果的にそうした普通のドキュメンタリストと違う経験が、他の人とは違うユニークな作品を手がける基礎になったんです。CGアニメの演出もやるし、バラエティー番組のセットも考える。だから、職歴を全部合わせたようなスタイルがバラバラのドキュメンタリーを作っていますね。それは、逆に自分の武器だと今では思ってますが。
【圡方】僕は十何年制作部というところにいて、ゼロから作っていくというところでずっとやってきたので、それはすごく活きています。すでにあるものを追いかけるという報道的な手法とはまったく違うということですね。『人生フルーツ』の伏原も同じ出自で制作から来ているんですが、最初から何となく意見が決まっていて、それを原稿に落としこみながら撮っていく、というのではないかたちであの作品ができたのも、他の場所にいたからというのはすごく大きいと思いますね。
【佐々木】思い返すと、自分はもともとゴリゴリのドキュメンタリーの方向へ行こうとしていたんですね。なんで今、こんな変則スタイルになっちゃったんだろうと思ったけど、逆にそれでよかったなとしみじみ思います。
【圡方】そこで学んだプロレスの技が生きているというか。
【佐々木】そう。目指すなら、プロレスもガチンコも強い猪木みたいな状態(笑)。
【圡方】それはすごい。だってドキュメンタリーにパンクラチオンの部分がないかといったら、なくはないですからね。本当に殴っている部分もあるし、基本的には本物のことが起きているから。それをより面白く見せるためのプラスアルファの部分を、他のいろんな番組で学ばれたんですよね。きっと。
【佐々木】そう言えば、圡方さんと会う前、僕らは圡方さんの番組を研究していたんですよ。『ホームレス理事長』を勉強会で流して、「これ、とんでもない番組だぞ」ってみんなで見ていたんですよ。2時間。
【圡方】みんなで集まってそういうものが見られる環境があるっていうのがうらやましいですね。
【佐々木】いきなりの体罰シーンも衝撃を受けましたね〜。「どうやって撮ったんだろう?」とか言いながら。
はぐれ者だから描ける物語
──冒頭で話されていたお二人のキャリアが、制作にも活かされているということなんですね。さきほど名前もでたジェームズ・マーシュ監督ももとは編集助手として業界に入ったというお話をされていて、繋がる部分があるのかなと思いました。実際の制作方法以外にも、ある種お二人自身の視点や考えが作品に反映されることがあるかと思いますが、そのあたりのことをもう少し詳しくお聞かせください。
【圡方】どんな作品でもそうですよね。バラエティーだろうがドラマだろうが、作り手の何かしらが投影されるわけで、それが醍醐味でもあります。あたかも一番客観性を帯びているであろうと視聴者に思われているものの中に自分の意見を、意識的にも無意識的にも含め投影させていくというか。
【佐々木】先ほど最近の自分の作品のことを言われて、経歴も確かにそうだなと思ったんですけど、基本的に自分が会社や組織の中ではぐれ者だから、取材対象もはぐれ者ばっかり選んでいるんですよ。
【圡方】僕もまったく一緒ですね。
【佐々木】『ボクの自学ノート』の梅田明日佳くんに対しても、自分を仮託して見ていたんだということに編集していく中で気付いちゃったんです。「結局、これは俺の話なのかも」って。これはちょっと恐ろしい話でもあるんですよ。他人の人生を使って自分の物語を語っているという話ですから。「おこがましい!」という話でもあるんですけど。
実際に構成の作業をしていると、構成要素の順番を並べ替える過程で、なぜか他人の物語が自分の物語にすり替わっていくことがあるんです。それが、フィクションじゃなくてドキュメンタリーでも起こるというイメージって、一般の人は持っていないんじゃないですかね。
【圡方】持っていないでしょうね。基本は。
【佐々木】いつも取材対象やテーマの話になりますもんね。でも、実は見せられているのは、作り手の、監督の、ディレクターの物語なんですよ。おそらく絶対に。『さよならテレビ』は、完全に圡方さんの視点ですよね?
【圡方】そうですね。あの作品を見たいろんな人から「何で社員を扱わなかったんだ」ってすっごく言われましたけど、結局自分がメインストリームの社員じゃないから、社員を選べないんですよ。外側から見ているから。
ある意味どこかで恵まれていない自分、はじかれている自分というのがあるが故に、そういう取材対象やテーマが作品になるので、悪いことばかりじゃないと思うんですね。メインストリームって物語として全然面白くないじゃないですか。負けていた人が最後に勝つのがウケるわけで、つまり世の中の人たちって実はマイノリティーの部分がすごくあるんですね。なので必ずしもマイナスばっかりじゃないなというのはすごく思います。
【佐々木】僕がもし大きな組織に入って、何の疑問も引っかかりも感じずにこれまで生きてきたら、描きたいテーマなんてなかったでしょうね。他の人と似たような構成で、同じような表現しか生み出せていなかったと思います。「3分の1の予算と期間ですごい番組を作ってやるよ」みたいな意地の張り方を、ずっとしてきたので。そういう中で鍛えられたなと今は思えます。渦中にいる時は、なかなか自己分析できないですから。
恐ろしいですよ、ドキュメンタリーって。作品が残っちゃっていますから、それを見ると、その当時の自分の精神状態や考えていたことが分かるので。他人の物語を描いていても結局、自分のことを思い出す。
【圡方】でもそれでいえば、ドキュメンタリーって本当に最高ですよね。役者さん以上にリアリティーを持った人たちで、自分が伝えたいことを世の中に伝えられるので。
ドキュメンタリーの未来
──では最後に。現代はテレビや劇場映画以外の場で発表されるドキュメンタリーも多くなってきていると思いますが、そのような状況に対してはどのように感じられているかお聞かせください。
【佐々木】今はあらゆる人が発信できるようになって、YouTubeを見る人も増えて、例えばトップYouTuberが「年収数億円、稼いでいる」なんて言われていますよね。だけど、10年後も今と同じようにワンショットでしゃべり続けるショート動画を毎日のように量産し続けている人生だったら、映像の作り手としてはかなりしんどいだろうなと想像します。稼いでいても、その作品作りには喜びがあるのかな、と。手法もやれることも限られてますからね。
だけど、YouTubeのようなメディアは今後も発展していくと思います。テレビが発展したように、映画が発展したように、YouTubeもメディアの発展史をほぼ同じように繰り返していくだろうと見ています。最近、YouTubeでも規制が増えてきていますよね。以前より無茶なことができなくなりつつある。テレビが辿ってきた道と同じことが起きている。石橋貴明さんのYouTubeが今、すごいウケていますけど、とんねるずの番組を手がけてきたバリバリのテレビマンが作っているから、YouTubeの動画でもめちゃくちゃテレビ番組っぽいんですよ。テンポやリズム、テロップの出し方や音響などなど。だから、将来的にはYouTubeもテレビ番組化していくだろうと見ています。実際、今でも再生回数が多いものはやっぱり構成がしっかりしている。1人しゃべりの動画でも、ちゃんと構成が練られていて、つかみがあって展開があり、オチがある。まさに三幕構成的に流れていくんです。5分とか10分のショート動画でも。つまり、YouTuberにも汎用性のある理論が実は『ドキュメンタリー・ストーリーテリング』には書かれているんですよね。映像制作に関わるあらゆる人が参考にして、指針になる本じゃないかと思います。
【圡方】僕はYouTubeはそんなに見てないですが、NetflixとかAmazonプライムとかああいう動画配信はめちゃくちゃ見ていますね。
【佐々木】海外のドキュメンタリーもかなり見られますよね。しかも、レベルが高い。先日、Amazonプライムで『同じ遺伝子の3人の他人』(2018年)を観たら、めちゃくちゃ面白くてびっくりしましたよ。最初の10分見たら止まらなくなります。最近見た中で、一番面白いドキュメンタリーでしたね。インタビューと再現映像と資料映像だけで構成しているんですけど、構成がすごくよくできているんです。ものすごく感情が揺さぶられるというか。そういうのをAmazonプライムの会員だったらタダで見られちゃう。気付いていないだけで、面白い作品を山ほど見られる時代に入っているんです。だから、本当にこれからの作り手は勉強しなくちゃいけないですね。
『同じ遺伝子の3人の他人』予告編
【圡方】そうですね。だからプロしかできないことっていうのをちゃんと身に付けていかないと。ラッキーで1回本当に路上のリアルファイトで勝ったというだけだと、ちょっと苦しいですよね。
【佐々木】YouTubeがどんどんテレビ化して、どんどんクオリティーが上がっていったら、素人が参戦しても戦えないですよ。よりhowを、作り方を勉強しなくちゃいけなくなります。この『ドキュメンタリー・ストーリーテリング』を今、YouTubeをやっている子たちが読んだら覚醒するかもしれないですね。撮影とか撮り方とか、映像の世界は奥が深いですから。カメラの機材をどう選ぶか、レンズは何を選ぶか、照明をどう組むか、技術の塊ですからね。いい作品を作れるようになるまでに覚えなきゃいけないことがたくさんあるんです。ワンショットで自撮りカメラだけやっていればいいと思っていたら、10年後は確実に飽きられていると思います。やれることが限られているから、自分自身も飽きてしまいますよね。でも、もっと視野を広げて、カメラを持って外に出て、何を撮るかみたいなことを始めたら、映像制作のブルーオーシャンが広がっていますよ。
【圡方】確かにその通りです。プロでちゃんとあり続けるためにいろいろやっていかなきゃいかんですね。
(完)
2020年10月3日収録
企画・構成:フィルムアート社
文字起こし:ブラインドライターズ
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。