フィルムアート社は会社創立の1968年に雑誌『季刊フィルム』を刊行して以降、この50年間で540点を超える書籍(や雑誌)を世に送り出してきました。それらどの書籍も、唐突にポンっとこの世に現れたわけではもちろんありません。著者や訳者や編者の方々による膨大な思考と試行の格闘を経て、ようやくひとつの物質として、書店に、皆様の部屋の本棚に、その手のひらに収まっているのです。
本連載では幅広く本をつくることに携わる人々に、フィルムアート社から刊行していただいた書籍について、それにまつわる様々な回想や追想を記していただきます。第3回目は、批評家・詩人の四方田犬彦さんに、創立のきっかけとなった映画批評雑誌『季刊フィルム』(68年〜74年まで)が発行されていた当時のことを振り返っていただき、ご著者である『人それを映画と呼ぶ』(84年)と『映画のウフフッ』(92年)が執筆された背景、また幻の日めくりカレンダー『映画暦』の創作の裏側についてご執筆いただきました。
『季刊フィルム』に始まる
1960年代が終わろうとするころ、草月ホールではさまざまな芸術的催しごとが開催されていた。欧米から実験音楽家を招聘したり、インディペンデントの映画祭を興して、日本の若い世代に個人映画の制作をしきりに扇動した説い。『季刊フィルム』はそうした文化運動の機関誌として最初は構想された。だがほどなくしてそれは、世界の映画の最前線に眼差しを向け、映画史と理論の双方を見据える強力な映画雑誌と化した。
『季刊フィルム』はわたしの知るかぎり、それは当時、世界でもっとも充実した内容をもつ映画雑誌であったはずである。ヂガ・ヴェルトフ集団の脚本?が紹介され、パゾリーニの映画理論とメッツの記号学が翻訳された。まだ公開も決まっていないのに、ドウシャン・マカベーエフの『WR』の脚本が掲載された。この大きなる開放系の雑誌は、日本のことなどに一瞥も投げかけなかった。ただ同志を糾合して事態の攪拌に務めることが、68年組には急務だった。なにかいってくれ。いまさがす。この標語が合言葉だった時代のことだ。
『季刊フィルム』のfrom page to pageの高校生読者であったわたしが、原稿執筆者としてフィルムアート社と関わるようになるのは、60年代後半の高揚と70年代の憂鬱を経過した後のことである。80年にロンドンのBFIでトランクいっぱい、映画書を買い込んだわたしは、それをそのまま四谷のフィルムアート社に預けた。そして前年に未知のノエル・バーチから贈られた『とおめにて 遠くの傍観者にとって』という日本映画論を、ぜひとも翻訳したいのだと申し出た。だがフィルムアート社にはもはや昔日の挑発的野心はなく、バーチの研究の独自性を読み解くだけの力量をもった編集者はいなくなっていた。彼らはハリウッドやヒッチコックをめぐり、カタログ風の案内書を刊行することで、かろうじて息を継いでいた。70年代という「鉛の歳月」の間に、日本の映画出版文化はひどく保守的な地点にまで後退していたのだ。60年代暮れの栄光を知る者に、それは残酷なことだった。
そこでわたしは方向転換をし、2冊の映画時評集をここから出した。『人それを映画と呼ぶ』(1984)と『映画のウフフッ』(1992)である。久しぶりに手に取ってみると、前者のなかにはその後わたしが大きく発展させていった主題が、夥しい数の種子を内に含んだ南国の果実のように詰められていることがわかる。ルイス・ブニュエル。朝鮮映画史。大島渚。地上から消滅したフィルムの文献による復元・・・。さりげなく文章のわきに書き留められたこうした事象への興味を、わたしはやがて膨らませ、大きな書物へと発展させていったのだ。
フィルムアート社ではもうひとつ、お巫戯け[おふざけ]の本を作った。『映画暦』といって1986年用の日めくりカレンダーである。これは本来、ドイツで毎年刊行されていたものにヒントを得て、その日本語版を冗談で創ってみようと考えこんだのである。デザイナーの鈴木一誌さんにもう一人編集者を加え、それぞれが持っているだけのスティール写真を段ボールに詰めて旅館に運び込み、気に入った順番に366枚を並べてみようという、突拍子のない企画である。吉永小百合の誕生日にはサユリの写真を、アンドレ・バザンの命日にはバザンの遺影を掲げた。鈴木一誌は渡哲也の気に入ったポルトレがないというので、わざわざ映画館まで出かけて行って、カメラでスクリーンを撮影してきた。こうしたことは、もし現在であったら犯罪なのかもしれない。だが世間の映画写真の扱いはまだひどくノンビリしたもので、試写会室に足を向けるなら、袋に包まれたスチール写真を何枚も渡されたものなのである。もっともこの日めくりカレンダーの刊行のおかげで、それ以後、配給会社がスチールの供給をしぼるようになったことは、書いておいてもいいだろう。
2010年代に入ってわたしが心強く思うのは、自分よりもひと世代年少の研究者のなかに、優れた映画史研究家が出現してきたことである。彼らはかつてのわたしのようにコスパの悪い試行錯誤もなく、大学院の静かな環境のなかで、豊かな映像資料に囲まれて、映画作家についての学位論文を執筆することができる。わたしはそれが素晴らしいことだと思う。だが残念に思うのは、その映画史的研鑽が現下に制作されているフィルムに何も寄与できずに、自己完結してしまっている点である。映画研究家は万事に慎重なあまりに、映画批評家として未知なる作家の未知なる作品を評価したり裁断したりすることができない。映画をめぐる二つの言説は、こうして水と油のように分裂してしまうことになる。この頽廃から映画言説を救い出すためには、運動体としての研究=批評誌の創刊が必要だろう。パリにはセルジュ・ダネイが創刊した『トラフィック』なる理論歴史研究誌が季刊で存在している。フィルムアート社もできれば往古の『季刊フィルム』の衣鉢を継いで、それに抵抗できるほどの季刊誌を創刊してみればどうだろう。もう『リュミエール』やら『カイエ・デュ・ジャポン』といった、多幸症的なバブル雑誌はいらない。映画を創る・観る・書くという行為が実りある循環運動として成立するには、そうした批評=研究のメディアがかならずや必要なのである。
『人それを映画と呼ぶ』
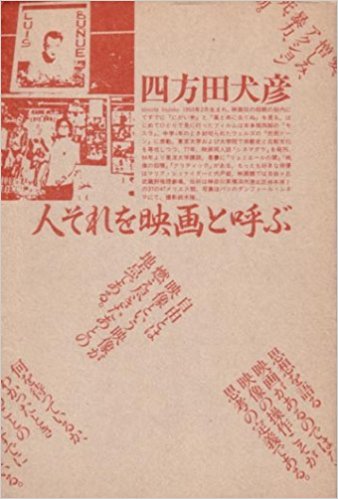
四方田犬彦=著
四六版並製|352頁|定価 1,800+税|ISBN 1074-8452-7414
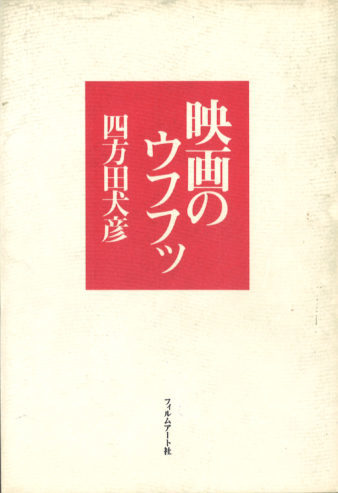
四方田犬彦=著
四六版並製|472頁|定価 2,800+税|ISBN 4-8459-9200-0
ブックシネマテーク別冊『映画暦 day cinema 1986』

四方田犬彦+鈴木一誌+稲川方人=企画・編集・構成
A5版変形・並製函入|定価 2,400+税|ISBN 0074-8558-7414

