十一月十五日
鴨といえば、南仏オック地方の名物料理「カスレ」が恋しい。土鍋に脂の乗った鴨とソーセージ、白インゲン豆を詰め込み、蒸し焼きにする。鴨肉もインゲン豆も溶け出した鴨の脂でこってり煮込まれる。思い出すだけで胸やけがする。脂まみれだと、塩味も感じにくくなるので、大量の塩も入っている。これを食べた翌日は、顔がむくみ、瞼が一重になる。一日中胸やけが続き、食事を抜く人もいる。一回食べると、寿命が一週間くらい縮まるのではないだろうか。食ったら後悔するとわかっているのに、やめられないカスレ。鴨に鴨にされているようなもの!? あのガチョウの脂肪肝フォアグラだってそうだ。フォアグラを食い過ぎて健康を害する人はガチョウに復讐されているのだ。
オレを食って死ね!
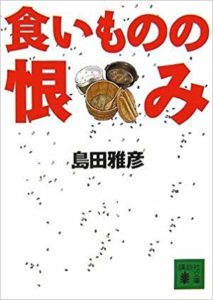
島田雅彦『食いものの恨み』(講談社文庫/二〇〇七)
今の時代ほど「無用の用」という考え方が軽んじられている時代もないだろう。バブル崩壊から就職氷河期を経て、デフレによって経済的な停滞を迎えている日本にはもはや余裕から生まれる表現が存在し難い状況になっている。ネットを目にしても、人々は他罰的な批判に忙しい。しかし、彼らが批判を抜きにしていったいどのような価値観を肯定しているかはあまり見えてこない。まるで自分と意見の違う人間を血祭りにあげることこそ目的のように思える。「余裕」どころか「楽しみ」も「優雅」も「無為」もどこかへ行ってしまった。現代の日本人にはお金もないなら暇もないから仕方のないことかもしれない。
近代の日本文学史を紐解いても、明治から戦後に至るまでは激動の時代が続いたので、明治後半から大正時代を経て昭和初期までのある程度の豊かさを作家が享受できたわずかな期間にのみ、余裕のある表現が登場したに留まる。この時期には永井荷風や谷崎潤一郎といった耽美派、志賀直哉や武者小路実篤の白樺派が活躍し、江戸川乱歩を中心とした推理小説が勃興し、横光利一や川端康成らのモダニズム、吉屋信子を中心とする少女小説が百花繚乱の様相を呈し、内田百閒や稲垣足穂のような独自の世界を追求する作家たちも現れた。このような豊かさに裏打ちされた表現が日本文学に戻ってくるには戦中・戦後を経て、経済が好況を呈する二〇世紀末を待たなくてはならなかった。今回取り上げる島田雅彦は村上龍、村上春樹、高橋源一郎らとともにこの二度目の豊かな時代を代表する作家だ。
私も就職氷河期の直撃を受け、不景気な二〇〇〇年代を苦々しい思いで過ごした人間のひとりで今も貧しいから、好景気の時代に活躍した作家たちを呑気なものだと思わないでもないが、彼らの作品には我々の世代にはない豊かさがあることは間違いない。私は嫉妬抜きで彼らを羨ましいと思う。私と同世代の書き手はバブル時代の作家を、その後も評価を高めていった村上春樹を除いてあまり重視しない傾向にあるが、私は優れた表現は豊かさに裏打ちされない限り、生まれ得ないと考えている。だからこそ、今度出す本は恐らく日本文学史上最も余裕のある姿勢を重んじ、「文学の楽しみ」を掲げた吉田健一に関する編著だし、いずれバブル時代の作家たちについて書く必要も感じている。
島田雅彦には「サヨク」だの、「ポストモダン作家」だの、「文壇の貴公子」だの、というレッテルがつきまとってきたが、こういった安直なレッテルは今や何の意味もなさない。不景気な二〇一八年現在とノンポリな空気が世間を覆っていた好景気の一九八〇年初頭では状況が違いすぎるし、ポストモダン思想を小説や批評に援用するのは凡庸どころか時代遅れになった。島田雅彦ももう「貴公子」という年齢でもない。逆にこうした陳腐なレッテルが剥がれ落ちた今こそ、ようやく島田雅彦を先入観に惑わされずに読める時期だと言える。
昨年、私は島田雅彦の著作を全作品(小説・評論・エッセイ・劇作・詩だけではなく、共著・編著も含めて文字通り全著作)読み返す機会があったのだが、そこにあったのは、今のような時代には重んじられないかもしれない豊かさだった。『亡命旅行者は叫び呟く』(福武書店/一九八四)は今読んでも笑えるブラック・ユーモア満載の諷刺小説だし、安易なアイデンティティを拒否することで逆説的にアイデンティティの探求を目論んだ『天国が降ってくる』(福武書店/一九八五)と『僕は模造人間』(新潮社/一九八六)は優れた青春小説だ。付け加えるなら、現在、『天国が降ってくる』と『僕は模造人間』の両作を読むことは、アイディティティ・ポリティックスのもたらす当事者意識の下、諍いの絶えない状況に解毒剤の役割を果たすだろう。夏目漱石の『こころ』をパロディにすることで、日本のインテリを最低人として戯画化した『彼岸先生』(新潮社/一九九二)もいい。あまり評価されていないバブル以降の小説にも良いものがたくさんある。自殺を決意した男の最後の一週間を描く『自由死刑』(集英社/一九九九)は島田雅彦のエッセンスが凝縮された成熟した作品で、個人的には随一の傑作だと思う。発表当時、金井美恵子や福田和也といった作家や批評家の批判に晒された「無限カノン三部作」(新潮社/二〇〇〇~二〇〇三)ですら、再読してみると、それまでのメタな作風をかなぐり捨て、真摯に物語を紡ごうとした試みだとわかった。残念ながら当時の純文学にはいまだポストモダンの残滓が漂っていたので、ストレートな「無限カノン三部作」は時代に先駆けすぎていたために攻撃に見舞われただけだ。『退廃姉妹』(文藝春秋/二〇〇五)や『悪貨』(講談社/二〇一〇)といった今世紀に入ってからの作品もストーリーテラーとしての冴えを見せている。
今回取り上げるのは島田雅彦の食日記と食エッセイを収録した『食いものの恨み』だ。薀蓄を振りかざす美食家気取りのエッセイはどれもこれも退屈だが、良い食エッセイというものは内田百閒であれ、吉田健一であれ、檀一雄であれ、獅子文六であれ、贅沢品であろうと粗食であろうと別け隔てなく、子供のような無邪気さで楽しんでいるから面白い。島田雅彦の食エッセイも同様で、なんでもかんでも食べるという姿勢があり、子供の頃からの読者だった私は、食と酒に関する姿勢は彼のエッセイに教わったと言ってもいいくらいだ。島田雅彦が自ら料理を作ることはあまり知られていないかもしれないが、『郊外の食卓』(筑摩書房/一九九八)と『ひなびたごちそう』(ポプラ文庫/二〇一〇)というレシピ本も出版している。悪食をしまくることで自殺を図る悪食博士という登場人物のエピソードまである『自由死刑』のみならず、自ら失踪した男の逃亡生活を綴った『ニッチを探して』(新潮社/二〇一三)も東京のB級グルメを網羅したような内容になっていることからわかるとおり、食は島田雅彦の小説の魅力的な要素でもある。
島田雅彦の食エッセイは飽くなき食物と酒への好奇心に貫かれている。偏食でキャベツの千切りで満足していた島田少年は酒を飲むようになってから食に目覚め、シベリア鉄道でロシア人とウォッカを空け、ベルリンで豚の生の挽肉を食べ、ヴェネツィアのバカーロ(立ち飲み居酒屋のようなもの)をハシゴし、中国の四川で火鍋に苦しみ、東京の下町の居酒屋を徘徊する。世界を股にかけ、美味いもの不味いもの区別なく味わう姿は『退廃礼讃』(読売新聞社、一九九八)や『酒道入門』(角川oneテーマ21/二〇〇八)で伺えるが、『食いものの恨み』はそのアジア版と言っていい。本書に台湾、屋久島や沖縄を中心とした南方、東北の食についてのエッセイと共に、日記形式で収録されているのが「痛快グルメ日誌 食いものの恨み」だ。
「痛快グルメ日誌 食いものの恨み」ではコンビニのカップ麺とおにぎりに始まり、上海蟹、ずくし、アンコウ、ホルモン、立ち飲み屋の鰻の串焼き、ちゃんこ、クエ鍋、大学の学食、韓国食べ歩き、インドでのカレー三昧の後、バンコク経由で帰国し、ふたたび日本での食生活という順番で書かれているが、美食日記といった趣きではまったくない。よくここまで毎日違うものを食べられるな、と感心してしまうほど雑食だ。あまりに節操がないので、逆説的に求道的なマゾヒズムすら感じてしまう。モスクワで闇キャビアを買って百グラム一気食いし、「黒いゲロを吐いた」というほどなのだから。
スノビッシュな気取りはかけらもなく、「一人前千七百八十円のクエ鍋」を頼んで「クエは何切れ入っているんですか?」と「貧乏臭い質問」をしてしまったり、『養老乃瀧』が金華ハムを使っていることに「やるな」と呟いたり、代官山のイタリアンの量が少ないとぼやく。その様は庶民的を通り越して意地汚いほどで、読んでいて欠食児童のような可愛さがあり、クスリとしてしまう。食エッセイでは描かれた食べ物を読者が味わってみたくならないようでは話にならないが、そういった店にも事欠かない。「ラブホテル街のど真ん中でフレンチ」という「露骨なシチュエーションゆえ」常連になったという渋谷円山町の『ビストロわいん亭』と両国の立ち食い鰻串焼き専門店『山田ちゃん』は美味しそうだったが、調べてみたら双方ともに潰れていた。仕方がないので、人とランチをしたついでにカスレを食べてみたのだが、本場フランスとは違い、日本のカスレはあっさりしており、翌日胸焼けを起こすこともなく、何か損をした気分になった。私もカスレを食べて苦しんでみたかった。食の道は厳しい。
「痛快グルメ日誌 食いものの恨み」は酒の話にも事欠かず、新宿で午前五時まで飲んでいたら、翌朝小田急線を乗り過ごし、江ノ島まで運ばれてしまったなど、本当にしょうもない話ばかりだが、このしょうもなさこそ、今は失われつつある「無用の用」という気がする。そもそも小説や随筆を読むということ自体が、他人の書いた作り話や身辺雑記を読むというしょうもない、無駄の極地のような行為だ。そして、島田雅彦は間違いなくその無駄を楽しむことを知っている。貧しい時代に生まれた私は同世代のご多分に漏れず、問題意識に踊らされがちだが、今こうやってこの原稿を書き終えつつあることだし、明日は久しぶりに遠出してビールでも飲もうか、何をつまみにしよう、などと考えているのだった。
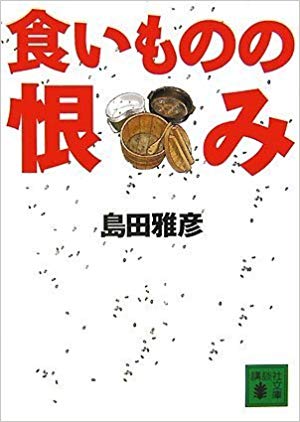
島田雅彦『食いものの恨み』(講談社文庫/二〇〇七)
バナー&プロフィールイラスト=岡田成生 http://shigeookada.tumblr.com

