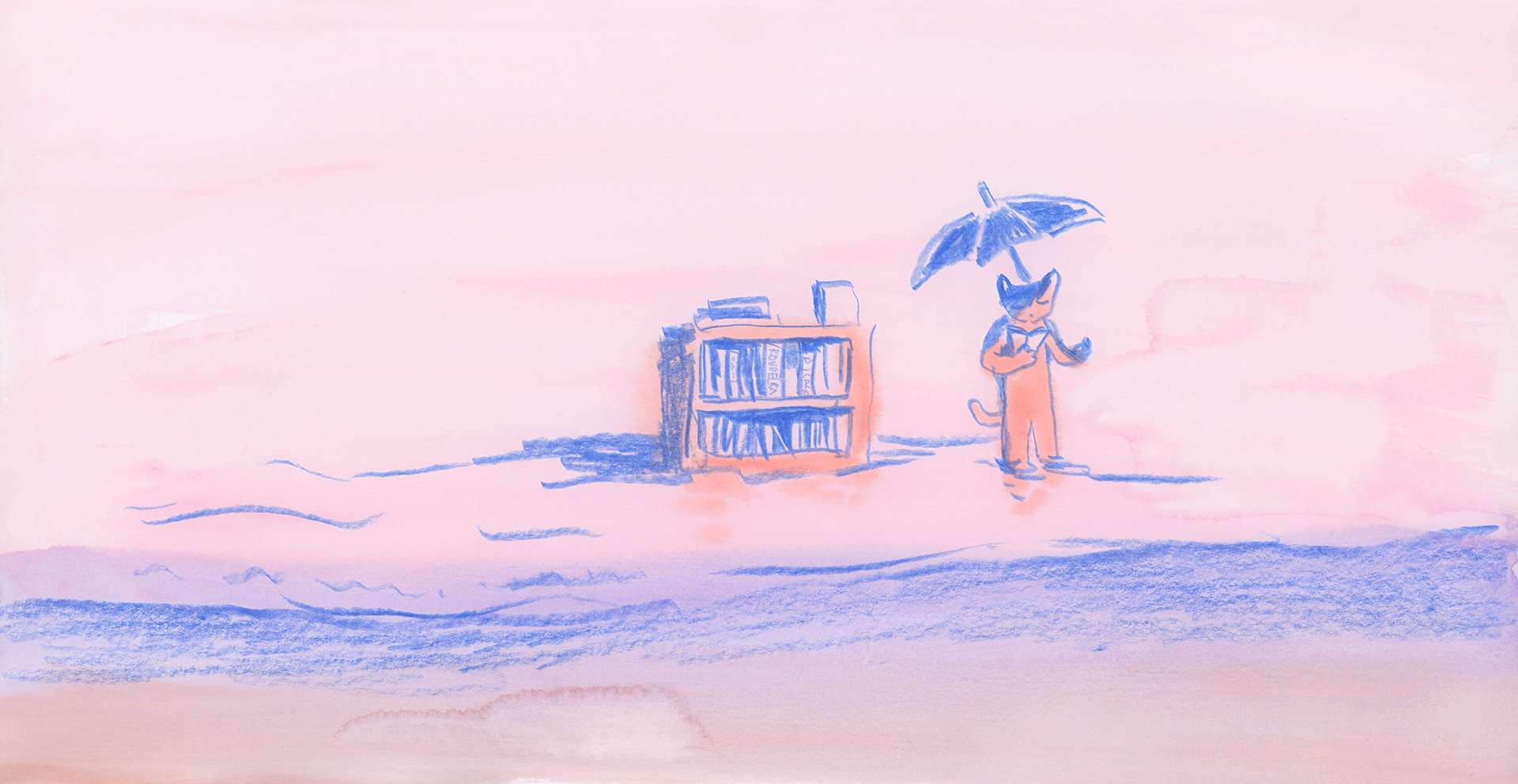2013年、東京・学芸大学の賑やかな商店街を通りすぎた先、住宅街にぽつんと、SUNNY BOY BOOKSは誕生しました。店主の高橋和也さんとフィルムアート社のおつきあいが始まったのはとても最近なのですが、ちょうど『ヒロインズ』を売りまくっていたり(250冊以上!)、企画展「想像からはじめる――Solidarity-連帯-연대――」が全国の書店を巻き込んだ大きなうねりとなって巡回されたり、すごいことを淡々と当たり前のようにやっていらっしゃる時期で、個人書店の底力というか、小さいゆえの機動力とか社会的な意義というか、改めて実感したのを覚えています。
以前のインタビューで「東京だからやっていける」とおっしゃっていた高橋さんですが、世の中の状況も変わり、決して楽観的ではないけれど、東京はもちろん地方でも本屋を始められる方がとても増えました。背景には、どこで買っても同じはずの本なのに、「大好きなお店を応援したいからここで買おう」と思う読者がすごく増えたことが大きいと感じます。SUNNYも特にコロナ禍初期に休業された際、心が折れそうなとき、お客さまからたくさんの激励を受け取って気持ちを保てたとのこと。だからこそ2021年2月に家族で沖縄に移住されることになっても、続ける意志が繋がれたのだと思います。
沖縄移住をすっぱり決断されたことといい、子供さんが生まれてからはより「生活」を大事にされる気持ちが強まったようにも感じます。ブレない軸を持ちつつも自然な流れに身を任せてきた高橋さんが、現実をどう受け入れ、これからどうなっていくんだろう、見守りたい方はたくさんいらっしゃると思います。高橋さんの考えややりたいことが少しずつ整理できるような連載になればいいなと思います。
前回の記事からこの3週間を振り返って、近所で相次ぐ水難事故、東北各地での記録的大雨、韓国の豪雨災害、北九州の市場での大規模火災、国葬騒動、内閣改造、77回目の終戦記念日、ペロシ下院議長の台湾訪問から高まる台湾有事など近くて遠い世界の出来事に目が回りそうになります。そんな気になるあれこれをお店の活動の中でも考えたり向き合う仕組みを作れないかなと思いつつ、まだ定休日すら決められない状況でお店と家のバランス取りにいっぱいいっぱいな日々を送っています。でも掃除、洗濯、御飯作りといった基本的な家事を続けていけるように時間を調整してきて、実際にお店を開ける前と変わらずに取り組めているのでよかったなと思っています。「生活」という基盤の上にお店の時間を作っていく、このことは沖縄でのお店を始める前からの目標(「第2回:なんとなく、でも確かに思っていること」に詳しくあります)だったのでこれからも忘れることなく、家族とともに生活を過ごしていきたいです。
そんな風に自分がこれからどうありたいのか、を考えていくことはお店の本棚にも影響していきます。というか、本棚とは過去も現在も内包した未来なのだと思います。本棚を見て「これ全部読んだんですか?」と聞かれることがありますが、僕の場合そんなことはありません。まだ読んだことのない本を仕入れることもあります。どこかで手にして目を通してみたり、細かく情報を調べてみて仕入れるかどうかは決めますが、最後はこの本を読んでみたいと思えるかというところで決めることが多いです。この「読んでみたい」という気持ちがこれから先どうありたいか、なのだと思っています。そしてそのことは同じような興味関心を抱いている方が来てくれたら嬉しいなとか、お店としてこういう場所になっていきたいなという小さな声になり、お店に来てくれる方との棚を通したコミュニケーションになっていくことがあります。先日ドライブがてら島に来て、集落を散歩していてたまたま「本と商い ある日、」を見つけたというご夫婦から「優しい気持ちになれる本棚ですね」と言っていただきました。お二人が受け取ってくださったものはまさにある日、がこうありたいと願ったことのひとつでした。それが本を選び、棚に並べることで伝わったということに静かに感動しました。これからもしっかりじっくりと本棚と向き合っていこうと思えました。

お店が開いた忙しさにかまけて、個人的に本を読むペースとタイミングが減ってきている(問題だ!)のですが、最近はこの春にやっと行けた新代田のエトセトラブックスで求めた古本『女たちの本屋』(アルメディア)を読み終えました。本の刊行は1993年ということで80年代にオープンした女性たちによる本屋が並んでいますが、初めて聞くお店ばかりでした。こんな本屋さんがあったのねーとパラパラとページをめくるようなものではなく、紹介されている本屋さんごとの思いと行動がめちゃくちゃに熱くて震えます。それぞれのお店ができるまでの経緯や家族やスタッフ、お客さんとのやりとりなど生活と密接に関わりながら、こうありたいと願い本屋をやる姿は色褪せることなく、むしろ輝きを放っているように感じました。この本に登場する女性や家族をテーマにした専門書店「ブックス家族」のメンバーが『過去二十年、女が自身を問う表現を書き継いできたのなら、男もまた今後二十年、同じくらい表現を模索していいはず。でなければ、本当の意味で「男と女は出会えないじゃないか」』(p.106)と投げかけています。最近はそういう意味で男性が自分語りをする本も増えましたが、40年余りが経ってもまだまだ少ないままだと言わざるを得ないでしょう。この本に登場する本屋さんたちの鋭くて切実な視点は、過去の本でありながら未来に生きるいまのわたしたちへの問いかけのようです。そう思うとき、私たちは生活のなかで本というバトンを繋いでいるようにも感じられたのでした。

そんな感じで振り返ることは未来への確かな足掛かりです。そこからこうありたいかたちへと繋がっていくのだと思います。そういう意味でこの連載は自分の今までの生活を振り返りながら「本と商い ある日、」という本屋のかたちを描いていく場所でした。書き始めた時はお店の名前も、場所も、何ひとつ決まっていない状況で、東京のお店から離れて少しホームシックになっている自分にひとまず何か書いてみますか? と提案してくださったフィルムアート社の津村エミさんには感謝の気持ちしかありません。連載が始まって宮迫憲彦さんも加わりおふたりがあたたかく見守ってくださったおかげで毎回なんとか書き上げることができました。初めは変なやつだなーとかつまらないやつだなーと思われるかなと気にしたり、それらしいことを言っているけど本当に自分にできるのかな、なんて不安になることが多かったです。今でも書いてしまった、言葉にしてしまったという気持ちになることが多いですが、だからこそやるしかないと切り替えて怯えながらも前を向くようにしています。ここに書き残した言葉を見返す度に、この連載が「本と商い ある日、」が出来るまでの間の、自分にとっての大切な居場所だったと感じています。もし読んでくれているあなたにとってほんの少しでも何かをトライすることの励ましになっていたり、前向きになれるようなきっかけになっていたら嬉しいです。ちょうど1年という節目でこの連載は終わりますが、ここからは「本と商い ある日、」という場所からの日々を積み重ね、まだみたことのない道を歩いていければと思っています。今までどうもありがとうございました。
いつかのある日、本のある場所でたくさんのあなたとの出会いを楽しみにしています。
2022年8月23日
本と商い ある日、髙橋和也